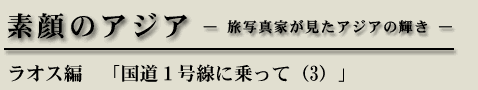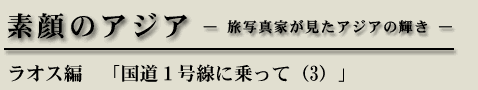|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
ラオス人はとてもシャイだった。特にラオス北部の山岳地帯には、カメラを向けられると恥ずかしがって顔を背けてしまう人が多かった。
見知らぬよそ者に対する人見知りの性質は、山に住むラオス人が生まれつき持っているもののようで、まだ生まれてから数ヶ月しか経っていない赤ん坊でさえも、僕がカメラを向けると火がついたようにわんわんと泣き出してしまうことがよくあった。
ラオス人の中でもとりわけシャイなのが年頃の女の子たちだった。もちろん中東のムスリム女性が見せる岩壁のような堅い拒絶に比べれば、ラオス女性のシャイネスなんてまだかわいらしいものなのだが、自然な表情を写真に収めることが難しいという点では、どちらも同じだった。
ラオス北部の辺境の地ビエントンで田植えをしている一家の写真を撮ろうとしたときも、田んぼの中にいた二人の女の子は、やはり恥ずかしがって顔を背けてしまった。そこで僕はサンダルを脱いで裸足になり、田んぼの泥の中に足を踏み入れてみた。あぜ道の上からカメラを構えるのではなくて、彼女たちと同じように田んぼに立てば、反応も変わるのではないかと思ったのだ。
田んぼという場所に慣れていない僕にとって、粘りけがある深い泥の中を歩くのは一苦労だった。右足を抜こうとして強く踏ん張ると、その反動で大きく左によろめき、左足を抜くときには反対に右に倒れそうになった。女の子たちは僕のヨタヨタした足取りを見て、声を上げて笑った。
|
 |
 |
僕の慣れない足取りが彼女たちをリラックスさせたのか、僕がもう一度カメラを向けたときには、二人ははにかんだ笑顔を見せてくれた。僕は続けて何枚かシャッターを切り、片言のラオス語で二人に名前を訊ねた。キャップを被った子がソンで、ニット帽を被った方がヒンという名前だった。
お互いの自己紹介が終わると、ヒンは手に持っていたひと束の苗をひょいとこっちに放ってよこした。
「田植えを手伝えっていうのかい?」
僕が身振りで訊ねると、ヒンとソンは「そうよ」といたずらっぽい笑顔で頷いた。もちろん冗談のつもりなのだろう。でも僕はそれを真に受けたふりをして、「それじゃ、始めようか」とシャツの袖をまくり上げた。女の子からの頼みを断るのは、僕のポリシーに反するのだ。
ヒンとソンは僕の意外な反応にびっくりしたみたいだったが、すぐに気を取り直して田植えのお手本を示してくれた。苗の束から何本かをちぎって、泥の中にぎゅっと差し込む。ちぎっては差し込む。ちぎっては差し込む。その繰り返しだ。
都会育ちの僕にとって、それは生まれて初めての田植え体験だったから、最初はなかなか上手く行かなかった。しかし、しばらく続けているうちに、だんだんとコツのようなものが掴めてきた。根の部分が泥で固くなっている苗を水に浸けて適当にほぐし、ちぎりやすくするのが手際よく植えるポイントだった。
ヒンとソンは共にまだ13歳なのだが、実にテンポ良く苗を植えていた。きっと幼い頃からこの仕事を手伝ってきたのだろう。ときどき僕の方を見てけらけらと笑い合ったり、民謡を口ずさんだりしながらも、二人は決して手を休めなかった。
そのようにして、僕らは苗を植え続けた。あぜに区切られた一面を植え終わると、休むことなく隣の田んぼに移った。僕はこうした単調な作業がもともと嫌いな方ではないのだが、90度に腰を曲げる姿勢をずっと続けるのは、さすがに辛かった。
「疲れたのなら、やめてもいいのよ」
僕が田植えを始めてから1時間ほど経った頃に、ソンが気を遣って声を掛けてくれた。
「いいんだよ」
僕は首を振った。そして空を仰ぎ見るようにして疲れた腰を伸ばしてから、再び田植えに取りかかった。朝から夕方までずっとこのきつい仕事を続けているヒンとソンの手前、わずか1時間で投げ出すわけにはいかなかった。
この日の田植え作業が終わったのは、西の空が見事な夕焼けに染まる頃だった。くすんだ色の夕陽が、ふたつ並んだお椀型の小高い山の間にゆっくりと沈もうとしていた。夕暮れ時の柔らかい光を受けた田んぼには、水面をすいすいと行き交うアメンボや、植えられたばかりの苗の上で羽を休める赤トンボの姿があった。
女の子たちが植えた苗は同じ間隔を保ってまっすぐ並んでいたが、僕が受け持った部分はとても不格好だった。植えることに夢中で、間隔まで気が回らなかったのだ。
それでもヒンとソンは屈託のない笑顔で「コープチャイ ライラーイ(本当にありがとう)」と言ってくれた。その笑顔が嬉しかった。
たった2時間ぐらいで、彼女たちの役に立ったとは思わない。でも、生まれて初めての田植えを終えた僕の中には、お金やモノではなく言葉でもない「何か」をお互いに交わすことができたという確かな満足感が生まれていた。
川の水の冷たさや、田んぼの泥の温もりを皮膚に感じること。それによって、僕らはその土地に住む人々に近づくことができるのだと思う。そこにある空気に馴染むことができるのだと思う。
|
|
|
|