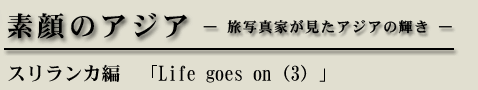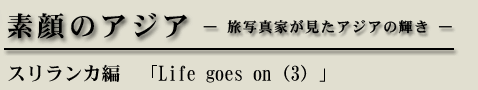|
 |
|
|
|
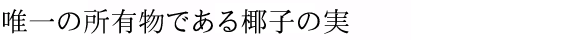 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| 廃材を組み合わせただけでも、雨風をしのげる家は作れる。 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
津波後のスリランカを旅している間、一度だけどうしても断り切れずに、現金を渡そうとしたことがあった。その相手はマネーロードから少し離れた海岸に廃材を利用した仮住まいを建てて住んでいるコラーセンという男だった。外観や雨漏りを気にせず、労力さえ惜しまなければ、一家族が暮らす家を作るのはそんなに難しいことではない。コラーセンさんはたまたま通りかかった僕にそんな風に言った。
「元の家はご覧の通り全部壊れてしまった。そこにトイレの穴があるだろう? 残ったのはあれと、家の周りに生えている五本の椰子の木だけなんだ」
コラーセンさんはそう説明すると、ほとんど唯一の所有物である椰子の実を、ナタで割って僕に振る舞ってくれた。日中の日差しがとても強く、すぐに喉の渇きを感じるスリランカ南部では、ほんのりとした甘味のあるココナッツジュースが水分補給には最適なのだ。中の水分を全て飲み干してしまうと、コラーセンさんは「中の果実をすくって食べればいいよ」とスプーンを渡してくれた。椰子の果実は上質のゼリーのように口に入れると柔らかくとろけた。
スリーウィーラー(オート三輪タクシー)のドライバーをしているというコラーセンさんの稼ぎは一日一五〇ルピー(一六〇円)。彼は自前のスリーウィーラーを持たず、雇い主から借りているので、その程度の稼ぎしか望めないのだという。それで一家八人が暮らしていくのは、普通であっても大変なはずだ。そこに津波が襲ってきたのだ。
「私たちを助けてくれないだろうか?」
とコラーセンが切り出したとき、「やっぱりきたか」と思った。正直に言って、彼が家の中の様子を見せてくれたり、被害の状況を話してくれたりする間、いつお金の話を切り出されるのだろうかと身構えていた部分があったのだ。
やはり彼もお金が目当てだったのか。僕はがっかりしながらも、今回ばかりは仕方がないな、とポケットから財布を取り出した。美味しい椰子の実をご馳走になっているのだから、そのお礼ぐらいはしなければいけないだろう。
「少ないですけれども、これは僕の気持ちです」
そんなことをもごもごと口にしながら、僕は財布から一〇〇ルピー札を取り出した。すると、コラーセンさんは慌てて僕の手を押しとどめた。
「ノー、ノー、そういう意味じゃないんだよ。私は一〇〇ルピーが欲しいわけじゃない。ただ、こういう事実を日本の人達に伝えて欲しいだけなんだ。そしてもし助けてくれるのであれば、津波の被害を受けた人みんなに援助をして欲しいんだ。これは私たち家族だけの問題じゃないからね」
彼はきっぱりとした態度でそう言った。顔が紅潮するのが自分でもわかった。「穴があったら入りたい」っていうのは、こういう時の気持ちを言うのだな、と思った。彼を最後まで信用できなかった自分がとても恥ずかしかったし、せっかくの彼の好意を裏切ってしまった気がした。
しかしなんという男だろう。津波で家を失いながらも自分の力で仮住まいを建て、通りかかった外国人の援助の申し出を断って、「みんなを助けて欲しい」と言う。誰もが自分の置かれた状況を嘆き、助けを乞うのが当然だという状況の中で、彼が見せた毅然とした態度は本当に眩しいものだった。
|
 |
 |
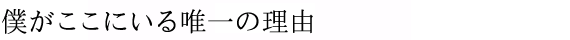 |
|
 |
|
|
|
そんな出会いがあってから、僕は「お金をくれ」と言われても、はっきりと「ノー」と言えるようになった。もちろん、その場でお金をあげるというのもひとつの選択肢である。でも僕は自分の信念に従って、そうしないことを選んだのだ。
今ここでお金をあげない代わりに、この場に起こったことのひとつひとつを記憶すること。自分の足で歩き、自分の目で見たことを、他の人に伝えること。それが僕がここにいる唯一の理由なのだと改めて思った。
元々、僕は使命感や義務感なんて全く持たずにスリランカにやってきた。マスコミの一員として派遣されているのなら、「被害の様子を伝えることが自分の責務だ」と自覚することもできるだろう。しかし一介の旅人にすぎない僕は、最初から町を歩く明確な理由を持たなかった。だからこそ、僕はいつも「何のためにここを歩いているのか?」と問い続け、「出会った人に対してどう振る舞うべきなのか?」と悩み続けなければいけなかった。それはとてもヘビーなことだった。日が暮れて宿に戻ると、いつもの町歩きとは全く違った種類の疲れがどっと押し寄せてきた。それでも僕は歩き続けた。歩き続けることしかできなかったのだ。
しかし、そのようにして無目的に歩き続ける中で、初めて見えてきたこともいくつかあった。それはマネーロードにたむろする即席物乞い達の不思議な明るさや、一〇〇ルピー札を受け取らなかった男の毅然とした態度、それに市街地の混沌とフォート内部の静寂とが隣り合わせになったゴールの町の不思議さだった。
一介の旅人として、ここに生きる人々とできる限り同じ目線でものを見ること。小さなリアリティーをひとつずつ積み上げていくこと。そうすることによって見えてきたツナミエリアの現実は、僕の中におぼろげにあった被災地のイメージとはかなり違うものだった。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| キリンダという漁村も大きな被害を受けていた。砂浜には津波によって打ち上げられた大型船が、その巨体を持て余すかのように放置されていた。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|