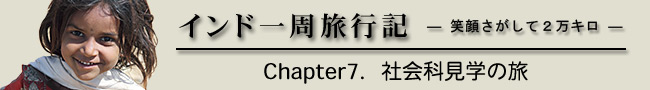|
|
|
 |
 |
 |
 |
カラフルな女とマッチョな男。インドで出会う人々は魅力的であると同時にフォトジェニックだったが、それはインドで立ち寄った町にも言えることだった。
インドの町にははっきりとした個性があった。野生の猿が我が物顔で歩き回る町もあれば、タバコ農家が集中する町もあり、唐辛子畑が続く光景があるかと思えば、男たちが椰子の木によじ登って椰子酒を採っている村もあった。美しい町もあったし、醜い町もあった。猥雑な町もあれば、のどかな町もあった。
それはコンビニチェーンと巨大スーパーとパチンコ店が延々と繰り返される日本の国道沿いの画一的な景色とは、まったく違うものだった。インドの町を歩けば、毎日なにがしかの発見や驚きがあった。感心させられることも、呆れかえることもあった。インドの町には自分の目で確かめられる余地がまだまだたくさん残されていた。
「さぁ、次の町には何が待っているんだろう」
僕はいつも少しの不安と大きな期待を抱きながら、バイクを走らせていた。
デカン高原南東部に位置するマダナパーリは、トマトの栽培が盛んな町だった。このあたりの土地は石ころだらけで痩せているので、稲を育てるのが難しい。だから乾燥に強いトマトを作っているのだ。
もっとも、ここがトマトの一大生産地となったのは、比較的最近のことだという。道路が整備されて都市への出荷体制が整ったことと、深い井戸を掘ってポンプで水をくみ上げる技術が導入されたことで、乾いた草を食べる山羊ぐらいしかいなかった土地がトマト農場に変わったのだ。
インフラの整備こそがトマト生産の鍵。それを僕に教えてくれたのは、マダナパーリのトマト市場で仲買人をしているラムチェンドラ氏だった。彼によれば、ここはインド最大規模のトマト専用市場であり、一日に700トン、金額にして200万ルピーものトマトが取引されているという。出荷先はインド各地に及び、南インドの中核都市であるチェンナイやバンガロールはもちろんのこと、1800キロも離れた首都デリーへも送られているという。
|
|
|
「北インドではトマトは夏場にしか採れないんだが、ここでは一年中収穫することが出来る。だから遠くまで運んでも採算が合うんだ。赤く熟したトマトはすぐに痛んでしまうから、近郊の町で消費される。大都市に送られるのは、まだ青いトマトなんだ」
ラムチェンドラさんはそう言うと、木箱から赤く熟した最高クラスのトマトを選んで渡してくれた。アメリカから輸入された種で、主にジュースに使われるということだったが、確かに果肉はジューシーで美味しかった。
「1キロだって2キロだって、食べたいだけ食べればいいさ」とラムチェンドラさんは笑いながら言った。「トマトだったら腐るほどあるからな」
実際、市場のあちこちには腐り始めたトマトが散乱していた。気をつけて歩かないと、トマトに足を滑らせて転びかねないほどだ。さすがはインド最大級のトマト市場である。右を見ても左を見ても、トマト、トマト、トマトだらけ。まるで赤いトマトの海の中にいるみたいだった。
|
|
|
トマトが入った箱をトラックに積み込むのは女たちの仕事だった。インドでは女性が男性と同じように重い荷物を頭に載せて働く姿は珍しくない。細身のインド女性のいったいどこにこれほどの力が備わっているんだろうと不思議になるほど、彼女たちはたくましかった。暇を見つけては仕事をさぼろうとする男性より、よっぽど有能じゃないかと思うほどだ。
市場で働く人々のたくましい働きぶりを眺めていた僕の目を釘付けにした一人の女がいた。彼女はプラスチックの空箱を頭の上になんと6個も積み重ねた状態で、すたすたと歩いていたのだ。これはすごい。まるでサーカス団員のような巧みなバランスである。
僕はすぐにカメラを構えてシャッターを切ったのだが、次の瞬間また別の意味で唖然とさせられてしまった。彼女は目的の場所に到着すると、その6個重ねの空き箱をそろそろと下ろすのではなく、そのまま地面にガチャーンと叩きつけたのである。彼女はそのまま平然と持ち場に戻り、再び空き箱を6個重ねて運んでくると、それをまたガチャーンと落とした。それがいつものやり方なのだろう。
|
|
|
いくらケースが頑丈にできていても、こんなに荒っぽい扱いを続けたらじきに壊れてしまう。もう少し丁寧な仕事はできないものかなぁと思うのだけど、ご本人は全く意に介す様子がない。
全員がそうだというわけではないけれど、インド女性の働きぶりはおおむねこんな感じである。確かに働き者なのだが、どうもやり方が雑というか、荒っぽいというか、最後の詰めが甘いのである。 |
|