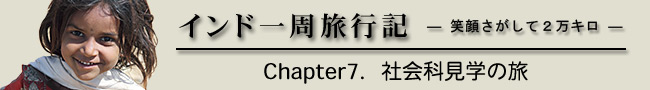|
|
|
 |
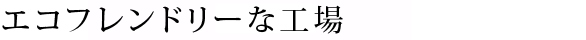 |
 |
 |
綿花畑と同じように、サトウキビ畑も南インドのいたるところで目にした。サトウキビは栽培に多くの水が必要なので、灌漑設備のある川の近くなどに多く見られた。
僕が興味を引かれたのは、収穫したサトウキビから砂糖を作るまでの過程である。これが実にシンプルでよくできたシステムだったのだ。
収穫されたサトウキビが運ばれてくるのは、畑の近くにある昔ながらの製糖工場だ。工場といっても、柱と屋根だけの簡素な小屋である。その横でサトウキビを搾っているのが一頭の牛である。お尻を叩かれながら歩く牛が特殊な歯車を回し、その歯車のあいだにサトウキビを差し込むと、汁が搾り取られるという仕組みだ。
搾られたサトウキビ汁は小屋の中に置かれた鍋に入れられて、グツグツと煮詰められる。この鍋は直径が3メートルほどもある。子供の頃読んだ絵本に出てきた、地獄で罪人を茹でるための大鍋を彷彿とさせる。
原液が煮詰まってドロドロになってくると、今度はそれを巨大なバットに移し替えて、長いヘラのようなものを使ってかき混ぜていく。
熟練した職人のヘラさばきは見事なものだ。二人の職人が協力して、ムラが出ないようにかき混ぜていく。しばらくそれを続けていると、次第にバットの中身が粘っこく固まってくる。
|
|
|
最後に固形化したものを手の平サイズに切り分け、布で水分をよく搾ってから、日陰で乾かすと完成である。
出来上がった糖は、白くてサラサラした『砂糖』とは違い、黄色くて粘りけのある『粗糖』である。不純物が多いために舌触りはざらっとしているが、コクがあってなかなか美味しい。この粗糖はすべて地元の市場に出荷されるそうだ。典型的な「地産地消」である。
僕がもっとも感心したのは、その無駄のないシステムだった。サトウキビ汁を搾っていた牛はサトウキビの葉を餌としていたし、原液を煮詰める際に使っていた燃料はサトウキビの搾りかすだった。サトウキビを育て、収穫し、搾り、煮詰め、かき混ぜる。その過程で無駄なものは一切なく、ゴミも出ない。全ては循環するひとつの輪の中にある。今風に言えば「エコフレンドリーなゼロエミッション工場」なのである。
|
|
|
もちろんインドにも近代的な製糖工場はある。そこでは上質な白砂糖が大量生産され、それは伝統的な粗糖作りを徐々にマイナーな存在へと押しやっている。
しかし、昔ながらの手作業に頼った製糖業もそう簡単には廃れないだろう。長年培ってきた知恵にもとづいた伝統産業が、地域経済で果たす役割はまだまだ大きい。インドの田舎を旅していると、そのことを強く実感するのである。 |
|