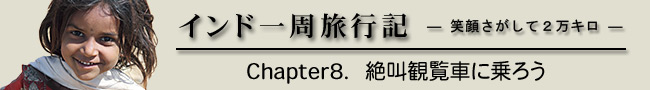|
 |
|
|
 |
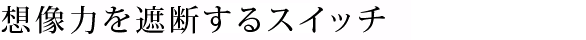 |
 |
 |
チャティスガル州に入った僕を待ち受けていたのは、とんでもない悪路だった。長い間メンテナンスが行われていないのだろう。いたるところでアスファルトが剥がれ、穴ぼこだらけになった無惨な道路が10キロ以上に渡って続いていたのだ。土埃がもうもうと舞い、不快な震動が絶え間なく襲ってくる。「インドの道・ワースト10」には間違いなくランクインする道であった。
インドでは州境を越えた途端に、道路のコンディションが激変することがよくある。道路の維持管理は各州の行政府の管轄なので、その州の台所事情が道路の状態に反映されてしまうのだ。豊かな州の道路はきれいだが、貧しい州の道路はひどくなる。これはもうはっきりしている。
もっとも、この道が悪路なのは事前に予想されていたことではあった。出発する前に、宿の従業員に「この先の道はバッド・コンディションかい?」と訊ねたのだが、彼は笑いながらこう答えたのだ。
「ノー。バッド・コンディションじゃない。ベリー・バッド・コンディションだ」
にもかかわらずこの道を選んだわけだから、誰を責めるわけにもいかなかった。自分で蒔いた種。自業自得である。
分かれ道にさしかかったとする。一方は整備の行き届いた幹線道路で、もう一方はデコボコの田舎道。こういう場合、僕はつい後者を選んでしまうのである。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| 自転車や牛車がのんびりと走る田舎道。地図には載っていない道だ |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
悪路を走れば、埃を浴びて全身が真っ黒くなるし、腰と尻が痛くなる。パンクの危険にも晒される。それはよくわかっているのだが、「ひょっとしたら、この苦難の先に何か面白いものが待っているのでは」という淡い期待が頭をよぎってしまうのである。「冒険心」とまでは呼べない、ちょっとした「怖いもの見たさ」の気持ちが、ムラムラと湧いてくるのだ。一種の病気である。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| 橋の建設現場。資材を引っ張り上げるのも人手に頼っている。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
実際、そうやって悪路を進んだ先に面白いものが待っていたってことも、ないわけではない(その数少ない成功体験が再び悪路を選ばせることになるわけだ)。
チャティスガル州東部に位置するサランガルという町で遭遇したのは移動遊園地だった。遊園地といっても、その中身は相当にチープなもので、アトラクションのほとんどは人力で動くものである。メリーゴーランドや回転するミニカーといった幼児向けの乗り物を、仏頂面をしたおじさんたちが黙々と手で回している。それでも、アトラクションの前には順番待ちの子供たちが行列を作っていた。一年に一度巡回してくるこの移動遊園地は、田舎に住む子供たちにとって数少ない娯楽なのだろう。
移動遊園地のメインアトラクションである大型の観覧車は、さすがに人力駆動ではなかった。高さは15mほど。頑丈な鉄骨製で、ゴンドラは全部で十二個ある。チープな遊園地にしてはなかなか立派なものだ。感心しながら見上げていると、切符売り場の男が、
「おーい、そこの外国人。これに乗って、上から写真を撮ってみなよ」
と声を掛けてきた。料金は10ルピーだがお前さんはタダで乗ってもいいよ、と言う。こんなところに外国人が迷い込んできたのが、よほど珍しかったのだろう。
お言葉に甘えて乗せてもらうことにした。ゴンドラの作りはちゃちだが、それ以外はごく普通の観覧車である。高さはそれほどでもないが、それでもてっぺん付近に達すると視界が開けてきた。特に何があるというわけでもない田舎町だが、二階建て以上の建物がほとんど無いこともあって、遠くにある森や溜め池まで一望にでき、眺めは良かった。
|
|
|
観覧車の操作を担当する眠たげな顔の男は、僕のゴンドラが頂点に到達したのを確認すると、わざわざ回転を止めてくれた。存分に写真を撮れ、ということらしい。僕は何枚かシャッターを切ってから、「もう動かしていいよー」と手を振った。
不吉な胸騒ぎを感じたのは、ゴンドラが再び動き始めたときだった。さっきまでとは明らかに動き方が違うのである。速いのだ。強い加速度がゴンドラにかかっている。
ひょっとすると、これは観覧車ではないんじゃないか?
その不安はゴンドラが一周した後さらにスピードを上げたことで確信に変わった。周囲の景色が一瞬で過ぎ去り、強い遠心力でゴンドラが大きく揺れた。やっぱりそうだ。これは景色を楽しむための観覧車などではなかったのだ。観覧車の外見をした絶叫マシーン。それがこの乗り物の正体なのだ。
もう写真撮影どころではなかった。眼下の景色を眺めている余裕もなくなった。両手で手すりをしっかりと握り締め、両足をぐっと踏ん張って、お腹のあたりがぞわぞわっと浮き上がってくるようなジェットコースター独特の無重力感に耐える。心臓は激しく波打ち始め、両手にはじっとりと汗がにじんできた。
断っておくが、僕は決して絶叫マシーンが苦手ではない。高所恐怖症の気もない。学生時代には関西でもっとも怖いといわれるコースターにわざわざ乗りに行ったこともある。でも、この「絶叫観覧車」の怖さは別次元だった。本物の恐怖だったのだ。
日本の絶叫マシーンは「事故は絶対に起こらない」という前提で運営されている。万が一でも事故が起きたら、遊園地の経営そのものが危うくなるからだ。マシーンには二重三重の安全対策が施されているはずだし、乗客もそれを信じて疑わない。だからコースターが「垂直落下」や「きりもみ走行」を行ったとしても、そこで乗客が味わうのは「とはいえ死ぬことはない」という安心感の元で体験される仮想的な恐怖なのだ。
しかしインドの「絶叫観覧車」が提供する恐怖は、決してヴァーチャルなものではなかった。スピードもGもたいしたことはない。けれどゴンドラには安全ベルトもないし、カバーも付いていないから、間違って手を離したら確実に振り落とされることになる。その恐怖はリアルだった。
安全管理にも疑いの余地があった。何しろここはインドなのである。機械の点検が入念に行われているとは思えないし、老朽化した観覧車のボルトが一本ポロっと外れたところで、たぶん誰も驚かないだろう。それにあの眠そうな顔をした係員! 我々乗客の命運はあんなやる気のなさそうな男の右腕に握られているのである。
不安になる要素ならいくつでもあって、それが頭を駆けめぐるたびに僕は新たな恐怖に襲われるのだった。
しかしもっとも驚くべきことは、冷や汗をかき、心臓を高鳴らせてゴンドラにしがみついているのは僕一人だけで、他の乗客は平然としているという事実だった。隣のゴンドラには十歳ぐらいの子供二人とその父親の三人家族が乗っていたのだが、三人ともゴンドラがぐんぐんスピードを上げても全く動じることなく、むしろそのスピードを楽しんでいるように見えた。さらに別のゴンドラに乗っている若者二人は、なんと座席から立ち上がって両手を離して踊り出したのである。これには開いた口が塞がらなかった。連中の頭の中は一体どうなっているんだ?
インド人は「想像力を遮断するスイッチ」を持っているのだ。僕はそう結論づけた。僕が感じる怖さの源には「もしかしたら落ちて死んでしまうかもしれない」という想像があった。最悪の事態をイメージすることが恐怖を生み出していたのだ。だから、そのような想像力を働かせるスイッチをパチンと切ってしまえば、恐怖は感じなくなるはずである。原理的にはそうなる。そしておそらく、多くのインド人はそうすることができるのである。
前にも書いたように、インドではバイクを運転する際にヘルメットを被る人はほとんどいない。にもかかわらず交通マナーは最悪で、無鉄砲に飛ばして命を失う人が大勢いる。これも「想像力を遮断するスイッチ」のせいだと考えられる。トラックやバスが一車線しかない狭い道路で抜きつ抜かれつのチキンレースを演じられるのも、ドライバーがその後に起こりうる悲劇をまったく考えないからである。
ある意味では、日本人とインド人は正反対の価値観を持っていると言える。前者は考えられる危険因子を注意深く徹底的に取り除くことをよしとし、後者は危険因子のことなど考えたって仕方がないのだからなるべく考えないようにする。
僕は何も「インド人が想像力に欠けている」とか「インド人は剛胆だ」などと言いたいわけではない。確かに危険に対する認識はいくぶん不足していると思うが、それはインドという荒っぽく無秩序なカオス世界をサバイブするためには、必要不可欠な性質なのだ。たぶん。
もし日本人の標準的な危機管理意識を持ったままインドで生活しようとすれば、三日で神経症になってしまうだろう。恐怖のあまり家の中から一歩も出たくなくなるに違いない。良きにつけ悪しきにつけ、ある程度の「鈍感力」を身につけなければインドでは生きていけないのだ。
「よー、外国人。このマシーンはどうだった?」
ようやく回転を終えた「絶叫観覧車」からよろめきながら降りてきた僕に向かって、切符売り場の男が声を掛けた。僕は心の中で「もう十分だ!」「早く止めてくれ!」と叫び続けていたのだが、その気持ちとは裏腹にゴンドラはなかなか止まらなかった。珍しい外国人が乗っているからと、いつもより余計に回してくれたのかもしれない。あの「染之助・染太郎」みたいに。はっきり言って余計なお世話だが、彼らを責めるわけにもいかなかった。悪意はないのだ。
「ああ、とてもエンジョイしたよ」
と僕は言った。精一杯の皮肉のつもりだったが、そうは聞こえなかったようだ。
「そうだろう。ぜひまた乗りに来てくれよな」
と男は屈託なく言う。この鈍感男め。
「ひとつ確実に言えるのはね、もう二度とこれには乗らないってことだよ!」
「そりゃまたどうして?」
男は不思議そうに僕の顔を覗き込んだ。彼はこの観覧車が愉快なアトラクションだと信じて疑わず、乗客が恐怖を感じているなんて考えてもいないようだった。
もちろん彼にも「想像力を遮断するスイッチ」が付いているはずだ。大いなる「鈍感力」を備えたインド人。僕がかなう相手ではない。
|
|
|
|
|
|
|