 |
|
|
 |
 |
 |
|
ダッカを歩いていて驚くのは、修理屋の多さである。
自動車やバイクや電化製品の修理屋はもちろんのこと、扇風機を専門に修理している職人や、古タイヤに新しい溝を彫るタイヤの修理屋まであった。穴の空いた雨傘には継ぎを当て、底の抜けたブリキのバケツには新しい底をくっつける。ありとあらゆるものに対して専門の修理屋がいるのだ。
まだ使えるものは何度も何度も直して使うのがバングラ流である。簡単にモノを捨てたりはしない。もし捨てたとしても、必ず誰かが拾って使う。日本だと「これ、修理するより新しいのを買っちゃった方が安いですよ」と言われてしまうことも多いが、この国では誰もそんなことは言わないのである。
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| 自転車は繰り返し修理して、ボロボロになるまで使う。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| これも修理屋の一種だろうか? 半分腐ったリンゴの腐った部分だけを取り除いて売るリンゴ修理屋は、おそらくバングラデシュでしか見られないようなレアな商売である。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
僕がダッカの街に着いてまずやったのも、壊れたサンダルを修理することだった。お気に入りのサンダルだったが、靴底がはがれてきて、とても歩きにくくなっていたのだ。
靴の修理屋はいたるところにあった。ゴムの靴底や針と糸などの修理道具一式を並べて地べたに座り込んでいるおじさんが、それこそ各ブロックごとに必ず一人はいるのである。靴屋1軒に対して、靴修理屋は10人ぐらいいるだろうか。
僕のサンダルを直してくれたのは、この道一筋何十年といった感じの実直そうな職人だった。彼はゴム底の裂け目にゴム糊を塗り込み、それを乾かしてから、太い針と丈夫な糸で縫い合わせていった。仕事も丁寧だったし、料金もたった20タカ(30円)だった。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| ダッカを流れるブリゴンガ川の川岸で、使用済みのビニール袋を洗って乾かしている女たち。どんなものでもリサイクルして使うのがバングラ人のやり方である。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| まだ使えそうなプラスチックをゴミ捨て場から探している。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| ゆうに30年以上は使われているだろう白黒テレビが捨てられることなく修理されている。 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
環境問題が注目されるにつれて、日本でもリサイクルという言葉をよく聞くようになったが、バングラデシュではそんな言葉が流行る前から、ごく当たり前にリサイクルが行われていた。モノが壊れても何度でも修理して使うというエコライフの基本が、バングラ人の生活の原点になっているのだ。
といってもバングラデシュは特別にエコ意識の高い国ではない。地球温暖化とか資源の枯渇を気にしている人は少ない。彼らは単に「その方が安いから」という経済的な理由で、ひとつのものを繰り返し使い続けているのだ。モノの値段に比べて人件費が圧倒的に安く、(僕がサンダルを直した時のように)ほんのわずかなお金で修理してもらえることが「捨てない社会」を支えているわけだ。
古くなったものはさっさと捨てて、常にニューモデルに買い換える浪費型社会の方が、GDP的には「豊か」になる。経済指標とはそういうものだ。お金やモノが回るスピードが速ければ速いほど、その社会は「繁栄している」と評価されるのである。
しかしそれは本当に豊かな社会なのだろうか?
|
|
|
 |
|
|
懐かしい活版印刷機も、この国ではしぶとく生き残っていた。ひとつひとつ活字を手で拾って文章を作り、それをハンコのように紙に押しつけて印字する、グーテンベルグ以来の超アナログな印刷機である。日本ではとうの昔に消えてしまったものが、リサイクル大国バングラデシュではまだ現役で働いていたのだ。
暗くて狭い印刷所では、二人の職人が働いていた。黙々と活字を拾って並べる男と、印刷機を操作する男。印刷機の動きはさほど速くなく、インクと活字とのあいだをローラーが往復するあいだに、手作業で紙を一枚ずつ交換する。おそろしくシンプルでわかりやすい構造である。壊れたってすぐに修理できそうだ。
「この機械はどれぐらい前からあるんですか?」
職人に訊ねてみた。
「100年以上だね」
彼は答えた。100年。それだけ使われたら、機械だって本望だろう。
100年前、この国はまだ英国植民地だった。その後インドとともにイギリスから独立し、東パキスタンとしてインドから分離し、そしてバングラデシュが建国される。時代は流れ、町の様子もすっかり変わった。人口も増え、通りには新しい店が建ち並ぶようになった。それでもこの印刷所は何も変わらなかった。同じスピードで、同じやり方で、ずっと文字を印し続けてきたのだ。
刷り上がったチラシはところどころ文字がかすれていたり、斜めに印字されたりしていた。そのばらつきが何とも懐かしかった。いとおしかった。品質やスピードではまったく勝負にならないけれど、活版印刷にはデジタル印刷には決して出せない味わいがあった。
|
|
|
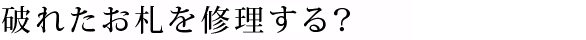 |
|
|
これを修理屋の中に含めていいのかどうかわからないのだが、僕が一番驚いたのは「お札の修理屋」だった。
その男たちは街角に小さなテーブルを出して、古くなったお札と新品のお札を交換していた。バングラデシュでは紙幣もボロボロになるまで使い続けるのだが、破れたり穴が空いたりすると、「こいつは使えないよ」と受け取りを拒否されてしまう。そういうトランプのババみたいな扱いを受けている古いお札をピン札に交換するのが、彼らの仕事なのである。
彼らの収入源はコミッションである。例えば半分に破れた5タカ札は3タカとして引き取り、ボロボロの500タカ札は450タカ分のピン札と交換するという。
で、破れたお札をどうするかというと、彼らはそれを「修理」するのだ。ボロボロにちぎれたお札をきちんと並べ直して、糊を塗った白い紙にぺたぺたと貼り付けていく。そうやって原形を回復させられれば、銀行に持っていって新品のお札に交換してもらうのだ。
日本の銀行でも、破れたお札を窓口に持っていけば新品に交換してもらえるが、バングラデシュではそれを代行する業者がいるのである。マネーロンダリング(資金洗浄)ならぬマネーリペアリング(貨幣修理)とでも言ったらいいのだろうか。
それにしてもセコい。あまりにもセコすぎる商売だ。
わずかな手数料のために小さなテーブルに向かってせっせとお札を貼り合わせている姿は、涙ぐましくもあり、どこか滑稽でもあった。
|
|
