 |
|
|
 |
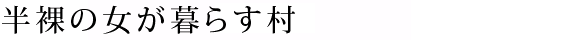 |
 |
|
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| ビルマ系のムルー族はベンガル人とはまったく違う顔立ちだった。 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
僕らが滞在することになったリンプン村は、人口184人の小さな集落である。ビルマ系の少数民族ムルー族(外国人にはムロン族と呼ばれることが多い)の人々が、川に沿って開けた傾斜地に暮らしている。
ムルー族はもともと狩猟採集生活を送っていたのだが、ごく最近になって米や野菜作りを始めたという。農業の開始に伴って、主食は森でとれるイモ類から米に変わったが、それ以外は昔とほとんど変わらない素朴な暮らしを送っている。電気も通っていないし、商店もない。村に部外者がやってくることはほとんどなく、外国人が来たこともない。なんと我々が歴史上初めてこの村を訪れた外国人になったのである。それぐらい閉ざされた土地なのだ。
村に足を踏み入れてまず最初に驚いたのは、家畜の多さだった。人よりも動物の数の方がはるかに多いのだ。鶏やアヒルや鳩、犬や猫、そして豚があちこちで寝そべったり、エサをつつき回ったりしている。基本的にすべて放し飼いである。ムスリムは豚を食べないから、豚がいる光景自体この国では大変に珍しい。
|
|
|
もちろん豚は貴重なタンパク源だから、日常的に食べるわけではなく、祭りや婚礼の宴といったハレの日のために大切に育てられている。鶏が生む卵も食べないという。卵は必ず孵化させて、大きく育ててから、町まで売りに行くのだ。現金収入に乏しい村人にとって、鶏は数少ない「商品」なのである。
その大切な鶏の羽根を一心不乱にむしっている若い女がいた。エサとなる米ぬかを地面に撒き、それをついばむために寄ってきた鶏を素手でひっつかまえて、強引に羽根をむしり取っていたのだ。羽根をむしられた鶏は「グゲー!」と苦悶の叫びを上げてその場から逃げ出すのだが、しばらくしてエサをまかれると、なぜかまたふらふらと女の近くに寄ってきて、さきほどと同じように捕まえられ、哀れにも羽根をむしられてしまうのだった。鶏の記憶は十秒も持たないのだろうか。ちなみにむしった羽根は楽器や耳かきの材料にするのだそうだ。
|
|
|
何十羽もの鶏が次から次に羽根をむしられていく光景はいわく言い難い迫力があった。その作業を特に感情を込めることなく淡々と続ける女の横顔も味わい深いのだが、何よりも驚いたのは、彼女が上半身裸だったことだ。背中には乳飲み子を背負い、腰にはスカートを巻いているのだが、豊満な乳房はまったくの無防備で外にむき出されているのだ。
ムルー族はごく最近まで半裸で暮らしていたらしく、今でも暑ければ上着を脱いで半裸になるのは珍しくないというが、「半裸のまま矢継ぎ早に鶏の羽根をむしる女」という絵には強烈なインパクトがあった。いやはや、なんだかすごいところにやってきたらしい。
僕らはリンプン村の村長の家に泊めてもらうことになった。ここに二泊して、村人の暮らしぶりや、村の生活改善のために活動するNGOの取り組みを撮影する予定だった。
「あんたらはチャクマか、それともガロか?」
開口一番、村長が僕らに訊ねた。「チャクマ」も「ガロ」もビルマ系少数民族の名前である。外見的にはムルー族とほぼ同じなのだが、住んでいる場所が違うし、宗教や言語も異なっている。いずれにしてもビルマ系民族の顔だちは日本人ととてもよく似ているので、村長が誤解するのも無理はなかった。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| バングラデシュ北部に住む少数民族ガロもビルマ系の顔をしている。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
「いいえ、僕らは日本人です」と僕は答えた。「ジャパンという国のことはご存じですか?」
「聞いたことはある」
と村長はベンガル語で言った。ちなみにこの村でベンガル語を話せるのは彼一人だけである。他の村人はムルー語しか話せないから、村の事情を訊ねるためには必ず村長を通さなければいけなかった。
「ジャパン。聞いたことはあるが、よく知らない」
村長も他の村人も「ジャパン」という国名から具体的に連想できることは何ひとつないようだった。学校もなければ、テレビもない、新聞もないし、都会に出たこともない。そういう人々にとって「外国」という存在はあまりにも遠いものなのだろう。彼らは長いあいだ半径数キロメートルの世界で完結する暮らしを営んできたわけで、日本がどんな製品を輸出していようが、アメリカの大統領が誰だろうが、中国の経済成長率が何パーセントだろうが、そんなことは日々の生活に何の影響も及ぼさない。知ったこっちゃない、のである。
村長の家は竹を組んで作った高床式で、家財道具がほとんどないので部屋の中は広々としていた。煮炊きに使う囲炉裏、鍋や釜の類、ナタやクワなどの刃物、ひょうたんを乾かして作った水瓶、山で使う竹籠などがこの家の持ち物のほとんどすべてである。
村人は生活必需品の大半を自分たちの手で作っている。例えば女たちが腰に巻いているスカートも、綿花を栽培するところから始めて、糸を紡ぎ、色を染め、織機で布を織るところまで、すべて自前で行っている。一枚の布を織るのに1ヶ月半もかかるというから、ずいぶんとまぁ気の長い話である。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| 昔ながらの織機で布を織る女性。雨季には増水した川によって外部との行き来ができなくなるので、ひたすら布を織る毎日だという。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
村長の家には古い電池式のラジカセがあり、それが唯一の「近代メディア」である。「RINSING」という耳慣れないメーカーの製品(たぶん中国製)だった。ラジオだけでなく、録音と再生ができるテープレコーダーが付いている。
村長が僕らのリクエストに応えておもむろに再生ボタンを押すと、スピーカーから奇妙な歌声が聞こえてきた。テープが伸びているのか、やたら音質が悪くて、メロディーも不明瞭だったのだが、耳を近づけて聞いてみると、何人かの男がお経らしきものを唱えているように聞こえた。
村長曰く、これはムルー族が信仰するクラマー教の儀式を録音したものだそうだ。クラマー教は古くからのアニミズム信仰と、宣教師によって伝えられたキリスト教が混ざり合った独自の宗教だという。
チッタゴン丘陵地帯に住む山岳少数民族の多くは、キリスト教の影響を受けている。リンプン村から歩いて1時間ほどのところにあるオナロン村に住んでいるトリプラ族も、全員がキリスト教徒だった。キリスト教の宣教師たちは辺境に住む「未開」の人々に神の恩寵を与えるというミッションを強く信じていて、そのためなら命をも投げ出す覚悟で布教にやってくる。そして布教活動と平行して、村に病院を建てたり、学校を作ったりすることで、村人からの信頼を得てきたのである。
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| トリプラ族の女性は首にたくさんのネックレスをかけている。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
