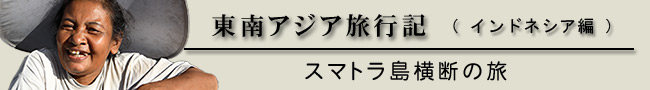|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
スマトラ島随一の都市メダンもジャランジャランの楽しい場所だった。路地は迷路のように複雑に入り組み、様々な音や匂いで溢れていた。ある窓からはカラオケ音楽が流れてきたし、別の窓からは夫婦喧嘩の声が聞こえてきた。アイスクリーム売りが鳴らす涼しげな鈴の音が聞こえたかと思うと、耳をつんざくような「アザーン」の声が大音量で響いてきたりもした。
そんな風にメダンの下町をあてもなく散歩していたときに、ユリコさんと出会った。
「ニホンジンデスカ?」
背後からいきなり日本語で呼びかけられたので驚いて振り返ると、軒下のソファに僕と同い年ぐらいの女性が座っていた。
「そうです。日本人ですよ」
僕が日本語で答えると、彼女は嬉しそうに微笑んだ。そして英語に切り替えて、「私のおじいさんは日本人なんです」と言った。そう言われてみると、一般的なインドネシア人よりも色白で、日本人に近い顔立ちのようにも見える。
「私の名前はユリコといいます。おじいさんが付けてくれた名前なんです」
ユリコさんの祖父であるキタオカさんは、太平洋戦争当時にメダンに進駐していた日本軍の兵士だった。1945年8月に日本が戦争に負けると、兵士たちの大半は故郷へ引き上げていったのだが、キタオカさんたち一部の兵士はインドネシアに留まることを選んだという。
その後キタオカさんはインドネシア軍の兵士となり、オランダ軍との独立戦争を戦い、イスラムに改宗してインドネシア人の女性と結婚し、子供が生まれ、インドネシアの市民権を得た。結局、1993年に75歳で亡くなるまで、キタオカさんは一度も日本に帰らなかったという。
「今から考えると、父は日本に残してきたものがなかったからインドネシアに留まることを選んだんだろうな」とキタオカさんの息子であるノリハッサンさんは言った。「これは父の戦友から伝え聞いた話だけど、父は日本がアメリカに負けたことをとても恥じていたそうだ。軍人として誇りが大きく傷つけられたんだろう。東京が焼け野原になり、広島と長崎に原子爆弾が落とされたと聞いて、日本の未来に絶望してもいたらしい。もちろん実際には、日本は世界が驚くような早さで復興したわけだが、その頃には父と日本とを結びつけるものはほとんど何も残っていなかったようだ。日本の故郷にいる家族とも連絡が取れなくなってしまったらしい」
ノリハッサンさんは日本語がほとんど話せないので、僕らの会話は英語で行われた。キタオカさんは家族の前でさえ全く日本語を使わなかったのだ。日本という国を捨て、インドネシア人になりきろうとしたのだろう。もっともノリハッサンさん自身は、子供の頃に日本語を教わらなかったことを後悔しているようだったが。
「父が日本語を口にしたのは、昔の戦友と話すときだけだったよ。とても楽しそうに話している姿をよく覚えている。その戦友たちももうこの世にはいない。戦争直後メダンには百人以上の元日本兵が住んでいたんだが、今でも生きているのは三人だけになってしまったんだ」
僕の祖父も南方戦線で戦った一人だった。ボルネオ島の密林の中で絶望的な行軍をさせられ、病や飢えによって仲間が次々と倒れる中、九死に一生を得て、日本に帰ってきた。その祖父も数年前に亡くなったので、僕のまわりには戦争の話を聞ける人が誰もいなくなってしまった。
しかしだからこそ、アジアを旅しているときに思いがけないかたちで太平洋戦争の傷跡やその記憶の断片と出会うことは、僕にとってとても貴重な経験だった。日本人の側からではなく、アジアの側から戦争を見つめること。そこで何が起こったのかを知り、それを記憶し続けること。そうすることによって、遠い過去の出来事でしかなかった戦争が、今の自分に繋がるものの一部として確かなかたちを取り始めたのだ。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| どぎつい色に塗られたカラーひよこ。一匹1000ルピア(13円)で売られていた。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
僕はノリハッサンさんとユリコさんが住む家に招かれて、夕食をご馳走になった。鶏肉のカレーとご飯、デザートには新鮮なパパイヤが付いた。カレーはインドネシア料理の常として舌が痺れるほどスパイシーなもので、食べていると額に汗が滲んでくるほどだったが、それに慣れてしまえばとても美味しかった。
ノリハッサンさんの家は広々としていて居心地が良かった。ユリコさんは銀行に勤めるOLで、ノリハッサンさんはメダンの日本総領事館に勤めている。インドネシアでも中流階級に属している一家らしく、生活にもゆとりがあった。
「うちの裏口は24時間開けっ放しになっているんです」とユリコさんは言った。「知り合いであれば、いつ誰が来ても歓迎する。それがインドネシア流のもてなし方なんです。もちろんあなたも同じですよ。いつでもお越し下さい」
それは単なるうわべだけの挨拶ではなかった。この家の勝手口は本当に開け放たれていて、僕らが夕食を食べている間にも、近所の人がふらっと立ち寄って雑談をしていったり、子供たちがお菓子をねだりにやって来たりした。大学で日本語を習っているという女の子が、日本人の来訪を聞きつけて遊びに来たりもした。
ガイドブックには「メダンはインドネシアで最も危険な町であり、近年凶悪犯罪が増加しているので注意が必要だ」などと書いてあるのだが、下町を歩く限り、そのような危険な兆候はまったく感じなかった。メダンはインドネシアでも有数の大都会だが、人々の間の緩やかな連帯感のようなものは失われていなかった。
夕食を食べ終わると、ユリコさんはステレオラックの中からお気に入りの音楽テープを選んで聴かせてくれた。その中には日本人の歌声も混じっていた。彼女のお気に入りは五輪真弓の「心の友」。これは1980年代にインドネシアで大流行した歌だという。インドネシア人なら誰もが口ずさめるほどヒットしたらしいのだが、僕にはまったく聞き覚えのない曲だった。日本人に馴染みの薄い歌が、なぜインドネシアで大流行したのかは大いなる謎だったが、ユリコさんもその辺の事情はよく知らないという。「ココロノトモ」という言葉が何を意味しているのかさえ誰も知らないというのだ。
それはともかく、「心の友」は哀愁のこもったいい歌だった。緩やかなメロディーラインと優しい歌声。それが熱帯で暮らす人々の心を打ったのだろう。
キタオカさんも生前この歌を聴く機会があったという。そのとき彼は何を思ったのだろうか。
「ところで、あなたはなぜこんな下町を一人で歩いていたの?」ユリコさんがふと思い出したように僕に訊ねた。「この界隈を旅行者が歩いているなんて滅多にないことなのよ」
「ただのジャランジャランですよ」
僕がいつものように答えると、親子は声を上げて笑った。知らない町をジャランジャランか。そりゃいいねぇ。
ジャランジャラン――目的も持たずにぶらぶらと歩き回ること。それによって僕は様々な人に出会い、シャッターを切り、町の空気を肌で感じてきた。
見知らぬ遠い島でしかなかったスマトラ島が、徐々に身近な存在として感じられるようになってきたのも、ジャランジャランのおかげだったのである。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|