|
 |
|
|
 |
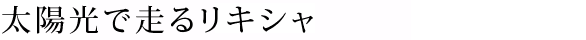 |
 |
|
その不思議な形をした三輪車は、チャッティスガル州ジャグダルプールにある市場の片隅に止まっていた。買い物用の三輪自転車の上にメタリックな青い屋根が取り付けてあるのだが、その屋根がどこからどう見てもソーラーパネルだったのである。

太陽光で走るリキシャ?
そんなものが存在するなんて聞いたこともなかったし、もちろん見たこともなかった。
僕が腕組みをしてこの奇妙な三輪車を観察していると、杖をついた老人がゆっくりと近づいてきた。
「この車に興味があるのかい?」
老人は流ちょうとは言えないまでも、なんとか理解できる英語を話してくれた。
「ええ、こんなものを見たのは初めてですから。これはあなたの車なんですか?」
「そうだよ」と老人は頷いた。「2年前に私が自分で設計して作らせたものだ。とてもユニークだろう?」
「この屋根はソーラーパネルなんですね?」
「そうだ。これは太陽光を使って走るリキシャだ。ソーラーカーのアイデア自体は、アメリカのテレビ番組からヒントを得たんだ。原理はとても簡単だ。私は電気技師だから、技術的にも実現可能だとわかっていた。問題はお金だった。ソーラーパネルはとても高価なんだ。1枚1万5000ルピーもする。それを3枚使っているから、パネルだけで4万5000ルピーもかかってしまった。バッテリーやモーターなんかを合わせると6万ルピー(9万円)もしたんだ」
「それは高いですね」と僕は言った。
インドではバイクが4、5万ルピーで買えるから、それよりも高価な乗り物だということになる。
「そんなに高価なのに、なぜソーラーパワーを使おうと思ったんですか?」
「ガソリンを使いたくなかったからだよ。ガソリンエンジンは空気を汚すし、燃料費もかかるし、騒音もうるさい。空から降り注ぐ太陽光ならタダで使えるし、空気も汚さない。こんなに素晴らしいものはないじゃないか」

74歳のサラン・ドゥベイさんがソーラーリキシャの製作に取り組み始めたのは、交通事故で片足を失ったことがきっかけだった。バイクの運転中にトラックと衝突し、右足の付け根から下を切断するという大怪我を負ってしまったのだ。一人で歩くのが難しくなったサランさんは、そんな自分でも簡単に運転できる乗り物はないかと探すうちに、このソーラーリキシャのアイデアを思いついたのだった。
「必要は発明の母だよ」とサランさんは言った。「もし事故に遭って片足を失わなければ、こんなことは考えもしなかっただろう」

ソーラーリキシャの製作でもっとも優先されたのはコストだった。サランさんは電気部品を売る店を経営してはいるが、決してお金持ちではなかった。だからなるべく安く作る必要があったのだ。そのためにソーラーパネル以外の部品は他の機械の中古品で間に合わせることにした。バッテリーは自動車用の鉛電池だし、フレームやブレーキや車輪も古い自転車から流用した。
「確かに美しくはないね」とサランさんは笑った。「はっきり言って醜い。それがこの車の欠点だってことは私にもわかっているよ。しかし一番大切なのは、この車がちゃんと走るってことさ」
サランさんの言うとおり、ソーラーリキシャは決して洗練された乗り物ではない。中古品を寄せ集めただけで、デザイン性なんてものは一切考慮されていないからだ。「ソーラーカー」という言葉から連想される未来的でハイテクなイメージとは正反対の、チープかつ手作り感あふれる機械なのである。
しかし実用性は十分にあるのだとサランさんは胸を張る。彼はこの車で毎日10キロほどの距離を走り続けているのだが、この2年間一度も大きなトラブルには見舞われていないという。
最高時速は15キロと自転車並みだが、特に急ぐ用事があるわけではないので、不便には感じていないという。フル充電で走行できるのは25キロ。晴天の日は外に駐車している間に充電できるし、曇りや雨の日には家庭用プラグから充電することも可能だ。さしずめ「プラグイン・ハイブリッド・ソーラーリキシャ」といったところか。
サランさんはもともと科学少年だった。実験器具を集めてきて電池を作ったり、メタンガスで動くエンジンを作ったりした。高校でもエンジニアリングを学び、卒業した後は電気部品を売る店を始めた。サランさん自身も修理技師として顧客を回ったおかげで、商売は順調に軌道に乗った。今は二人の息子が店の経営を引き継いでいる。
「私は毎朝必ずヨガをするんだ。この習慣は片足がなくなってからも欠かしていない。この車も毎日のメンテナンスが欠かせないが、自分の体も同じだよ」
その言葉通りサランさんは活力に満ちていて、片足を失った74歳の老人とはとても思えなかった。交通事故はショッキングな出来事だったが、いつまでもそれを悔やんでいても仕方がない。なんとかして自分の「足」を作り出さなければいけない。その思いがソーラーリキシャを誕生させたのだ。
サランさんはいつものようにソーラーリキシャを運転して自宅に帰っていった。ソーラーリキシャはおそろしく静かに発進して、ゆっくりと加速していった。まったく無音のまま、まるで氷の上を滑るように町を走り抜けていく。

ジャグダルプールのような小さな町でも、メインストリートの交通量はかなりのもので、バイクのエンジン音やトラックのクラクションノイズが昼夜を問わず町を満たしていた。この騒音の海の中を、しずしずと進んでいくソーラーリキシャの後ろ姿は、なんだかとても痛快でカッコ良かった。外見は無骨そのものだが、ひときわクールな存在感を放っていた。
「今から30年後には、こんな車が当たり前になっているかもしれないね」とサランさんは楽しそうに言った。「みんなが電気自動車や電動スクーターに乗るようになったら、インドの町は静けさを取り戻すだろう。それはとても素晴らしいことだと思う。私がそれをこの目で見ることはないだろうが、そんな未来を考えただけで楽しくなるんだよ」
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
