 |
|
|
 |
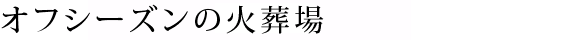 |
 |
|
遺体を火葬にしてその灰をガンジス川に流すのは、聖地バラナシだけで行われている特別なことではない。実はガンガーの河岸にはいくつもの火葬場が点在していて、日常的に火葬を行っているのである。
バラナシを出発した僕は、蛇行するガンガーに沿ってビハール州を東へと進んでいたのだが、行く先々で火葬場から立ちのぼる白い煙を目にすることになった。
ビハール州ナーランダー県では、火葬の一部始終を撮影することができた。バラナシの火葬場では写真撮影は厳禁なのだが、ここでは撮影禁止どころか、遺族から「ぜひ撮ってくれ。アドレスを書くからあとで写真を送ってくれ」と頼まれたのである。これには僕の方が驚いてしまった。
亡くなったのがデヴィさんという80歳の老婆だということも、火葬場の雰囲気をおおらかなものにしていたのかもしれない。天寿を全うした人がガンガーに還るのは、悲しむべきことではない。人々のあいだにはそんな意識が共有されているようだった。
火葬場を取り仕切る男によれば、ここがもっとも混み合うのは冬だという。病人や老人には寒さが一番堪えるからだ。その次が夏。夏と冬の間に挟まれた今の季節は、一年でもっとも死者の数が少ないという。
「今はオフシーズンだね」と火葬場の男は笑った。「冬は本当に忙しいんだ。今日ぐらい暇なのがちょうどいいね」
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| 黄色い布で包まれた遺体は竹でできた担架に載せられている |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
オフシーズンとはいえ、火葬場には次から次へと遺体が運び込まれていた。遺体は親族の男たちが担いでくる場合もあるし、バスの屋根やトラクターの荷台に乗って運ばれてくる場合もあった。老いた人もいれば、働き盛りとおぼしき男もいた。我が子の遺体を両手で抱えながら歩く父親の姿もあった。白い布に包まれたその遺体の手足は小枝のように細かった。伝染病にでも罹ったのだろうか。父親の表情は硬く険しかった。
|
|
|
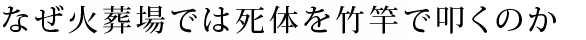 |
|
|
デヴィさんの火葬の準備は手際よく進められていた。薪を交互に組み、川の水で洗った遺体をその上に載せてから、火がつきやすいように枯れ葉やワラをかぶせていく。薪のあいだから見えるデヴィさんの顔は、眠っているかのように安らかだった。息をしていないということが信じられないほど生々しかった。


準備がすべて整うと、デヴィさんの息子が薪を覆う枯れ葉にマッチで火をつけた。風が強い日だったので、薪はものの数秒で勢いよく炎を上げ、たちまち大きな火柱へと成長した。最初に髪の毛がチリチリと音を立てて燃え上がり、やがて顔に水ぶくれがいくつもでき、腕の皮膚が黒く焦げていった。動物の肉が焦げるときのにおいがあたりに漂いはじめた。

親戚一同はその様子を少し離れた場所から無言で見守っていた。特別な祈りを捧げる人はいない。涙に暮れている人もいない。すべてが終わったあとの安堵感のようなものを漂わせながら、燃えさかる遺体をじっと見つめていた。
しばらくして火の勢いが落ちてくると、長い竹竿を手にした火葬職人がやってきて、遺体を叩きはじめた。遺体が燃え残るのを防ぐために、こうやって肉をバラバラにほぐす必要があるという。そうしないと遺体の表面が黒く焦げるだけで、肉の中にまで火が通らないのだ。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| 火葬職人はしたたる汗を拭いながら、淡々と自分の仕事をこなしていった。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|

火葬職人が繰り出す打撃はまったく遠慮のないものだった。大きくしなった竹竿が、遺体の腕や頭に打ち下ろされていく。特に燃えにくい頭部には、もっとも激しい打撃が加えられた。「バシッ!」「クシャ!」という乾いた音があたりに響き渡り、はっとするほど赤く生々しい肉の色があらわになった。
こうしてかつて老婆であった肉体は、内臓をえぐられ、肉汁を飛び散らしながら、徐々に原形を失い、黒く崩れていった。

僕は親族とともにその一部始終を見つめていた。
なぜ俺はここにいるんだろうと思いながら、それでもシャッターを切り続けた。
目の前で繰り広げられているのは、見方によってはグロテスクで異様な光景だったが、それをありのまま受け入れてしまうと、不思議なほど静かな気持ちになった。
死者を灰に帰するための炎は、生と死の狭間でゆらゆらと揺らめきながら、強烈な熱を放射し続けていた。
死者のにおいが漂っていた。それは僕の服や髪の毛にも染みこんでいた。このにおいは洗ってもしばらくはとれないだろう。そんな気がした。

火葬が終わったのは、薪に点火してから一時間が過ぎた頃だった。用意した薪はすべて燃え尽きてしまったのだが、火葬職人の奮闘にもかかわらず、かなりの大きさの肉の塊が燃えずに残されていた。
親族の男たちは燃え残った遺体を改めて布で包むと、ガンガーへと投げ入れた。それは大きな放物線を描いて着水し、さざ波とともに川の中に消えた。
燃やされる薪の量は、火葬場に支払うお金によって決まるのだそうだ。デヴィさんの一族は貧しい農民なので、火葬場に支払ったのはわずか251ルピーだった。それでは遺体を完全に燃やせるだけの薪は用意できないので、一部が燃え残ってしまったのだ。
「お金持ちだと5000ルピー以上払うこともあるんだ」
と火葬場を取り仕切る男は言う。お金持ちの火葬では質の良い薪を大量に使うことができるので、遺体が燃え残るようなことはないのだそうだ。「地獄の沙汰も金次第」という言葉があるが、インドでは「解脱への道も金次第」なのかもしれない。
「でも燃やしてもらえるだけマシなんだよ。火葬にできない人だっているんだからな」
火葬場のしきたりでは、子供や妊婦、事故に遭った人や、蛇に噛まれて死んだ人などは、火葬にせずにそのままガンガーに流されるという。そのような遺体は黄色い布に包まれたまま船に乗せられ、川の中程まで出たところでドボンと川に投げ込まれるのだ。重しとなる石を足にくくりつけてはいるものの、やがてそれが切れると、遺体は水面に浮き上がってくる。大河ガンガーはそのような腐敗した亡骸をいくつも飲み込みながら、悠然と流れているのである。
|
|
|
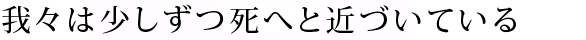 |
|
|
僕が目にした火葬場の日常は、確かに残酷なものではあったが、決して暗く湿っぽいものではなかった。むしろ拍子抜けするほど明るく、あっけらかんとしていた。火葬の一部始終はすべてオープンにされていて、見ようと思えば誰もが見ることができた。隠す意識など元からないようだった。インドの人々にとって「死」は特別なものではなく、すぐそばにある日常風景なのだ。
言うまでもなく、それは僕らが知っている日本の火葬とは大きく違うものだった。日本人は死を「穢れ」として日常から遠ざけ、死そのものをなるべく直視せずに済むようにしてきた。今では大半の人が病院で息を引き取り、専門家の手によってクリーンで清潔な火葬場に送られて、短い時間で白く乾いた骨となる。確かに清潔でシステマチックなやり方だが、それによって何か大切なものが失われているような気もするのである。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| 火葬が終わると、その場に立ち会った人々はガンガーの水にざぶんと頭まで浸かる。この沐浴には、聖なるガンガーの水で穢れを落とすという意味がある。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| 沐浴を終えた男たちは白い服を風にさらして乾かし、家路に就く。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|

「人生の最後にはガンガーに還る。それがインド人なんだ」
火葬場を取り仕切る男は穏やかな水面を眺めながら言った。それは比喩でも何でもなく、今ここにある現実そのものだということが、僕にもよくわかった。
人はいつか必ず死ぬ。死んだ人間は火葬場に運ばれてきて、薪とともに燃やされ、ガンガーの中に消えていく。茶色く濁った大河の一部となり、やがてあとかたもなく分解される。そして再びどこかで新たな生命として生まれ変わるのだ。
輪廻転生。それを信じているヒンドゥー教徒は、だから墓を作らない。
動物も人もひとつの大きな輪の中にいて、それをゆったりとかき回しているのが、悠久の大河ガンガーなのである。

このような世界観に立ってものごとを眺めたとき、人生ははかなく有限であることを思い知らされることになる。自分が生きている意味など無きに等しく、毎日少しずつ死に向かって進んでいるだけの存在なのではないかという気持ちにもなってくる。
しかし同時にそこには深い安らぎもある。
人はいつか必ず死を迎えるが、それは大いなる流れの中に戻っていくだけのことであって、恐れる必要などない。ただその流れに身を任せていればいいんだ。そんな風にも思えるのだ。
インドの人々は日常的に火葬の場面に立ち会うことによって、自らの死を想い、死を受け入れる準備をしているのかもしれない。親戚縁者が炎に包まれ、黒く焦げながら崩れていく様を見守るということは、死者への弔いであると同時に、いつかこれと同じことが自分の身にも起きるのだと自覚することにも繋がるはずだ。


我々は今を生きながら、少しずつ死へと近づいている。
火葬場の炎は、それを言葉ではなく、皮膚感覚を伴った方法で伝えている。
人はみんな生きていて、やがて死んでいく。
そんな当たり前のことを確かめるために、僕は旅をして、写真を撮っている。
|
|
|
|
|
