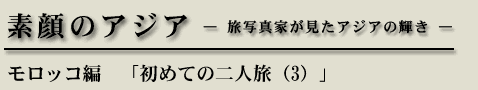|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| ジャマ・エル・フナ広場には様々な大道芸人たちがパフォーマンスを行っている。ヘビ使いは特に有名だ。 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
僕とウィリアムはモロッコを旅した1ヶ月のあいだ、ずっと一緒に街を歩き回り、同じ部屋に寝泊まりした。僕は結婚も同棲もしたことがないし、旅はいつも一人だったから、他人とこれほど長く一緒に過ごしたのは生まれて初めてのことだった。
この期間限定の共同生活は、基本的にはとても上手く行った。僕の英語力が未熟なせいで、僕らのコミュニケーションは完璧とは言いがたいものだったが、かえってそのことが二人のあいだに適度な距離感を保つことに繋がったのではないかと思う。
それでも、些細な点で意見がぶつかることはよくあった。シャワーの使い方とか、歯の磨き方とか、そういうことである。僕がホテルの部屋にいろんなものを置きっぱなしにしたままで外に出かけることも、ウィリアムは気に入らないようだった。誰かに盗まれることを恐れていたのだ。
「今まで長く旅をしてきたけど、ホテルの部屋にものを置いて盗まれた経験は一度もないんだ」と僕は説明した。「それに、ちょっと食事しに行くだけなのに、パソコンを持って出るなんて面倒じゃないか」
「それは君がたまたま運が良かったってだけさ。ここでもその運が続くとは限らない」
「大丈夫。僕は運がいいんだ。信じてよ」僕は笑って言った。
「ねぇマサシ、やっぱり心配だよ」ウィリアムは腕組みをして首を振った。「たぶん僕がそう感じるのは、育った環境のせいだと思う。僕が生まれ育ったロサンゼルスでは、どんなときでも気を抜くことができなかった。ホテルの部屋に荷物を置いたら、従業員が盗むんじゃないかと心配になるし、スーパーで買い物をしている間も、駐車場に置いてきた車のことが気になって仕方がない。子供を一人で外に出して遊ばせるなんて絶対にできない。そういう街だったんだ。特に僕らの仲間、黒人には悪い奴が多かった。金のためなら平気で人を殺す奴もいたんだ」
隣人を信用するな、というのがアメリカ人の常識なのだとしたら、それはとても悲しいことだと思う。いつも何かを盗まれるんじゃないかと恐れなくてはいけない街が、日常生活を営むのに相応しい場所だとは到底思えないからだ。
「僕も日本に住むようになって、ずいぶん変わったよ。安心して暮らしてもいいんだと思えるようになったんだ」
と彼は言った。彼が今、家族と共に暮らしている山陰地方の街は、LAとは正反対ののんびりした土地柄なのだという。もちろん殺人事件とは無縁に近い。
「それでも、30年間危険な街で過ごした記憶は、簡単には消えないよ。一度、家族が寝静まった真夜中に、不審な物音で目を覚ましたことがあったんだ。妻は隣で眠っているし、子供も起きてはいない。でも、確かに誰かが家の中でごそごそやっている音がするんだ。僕の心臓は高鳴った。ちょうど日本のどこかの町で一家全員が惨殺されるというニュースを見たばかりだったから、そいつがここにやってきたのかもしれないと思った。いろんなことが一瞬のうちに頭を駆け巡った。もちろん寝室にはナイフもないし銃もない。武器になりそうなものは何ひとつなかった。だから僕は自分の左手を強く握りしめて、いつでもパンチを繰り出せるような態勢で、扉に近づいたんだ。向こうにいる『ヤツ』の足音は、どんどんこっちに近づいてくる。心臓はバクバク音を立てている。僕は左手を強く握しめる。そして扉を勢いよく開けて叫んだ。『てめぇ、なにやってる!!』」
ウィリアムはそう言って、左手のこぶしを高く振り上げた。彼が繰り出したパンチは、僕の顔の直前で止まった。迫真の演技に、僕は少したじろいだ。
「……僕が殴りかかろうとした相手は、妻だった。そう、全ては勘違いだったんだ。彼女はただトイレに起きただけだった。僕は彼女の布団がふくらんでいるのを見て、そこに寝ていると思い込んでしまったんだ。妻はわけがわからずに震えていた。突然、夫が殴りかかってきたわけだから、当然だね。僕は事情を説明して謝った。馬鹿な話だ。でも、その時は本当にシリアスだったんだ」
その時もしウィリアムが勢い余って奥さんを殴ってしまったら、笑い話では済まされなかっただろう。もし部屋の中に銃やナイフがあったとしたら、もっと恐ろしいことになったかもしれない。実際アメリカでは、その手の勘違いによって自分の家族を殺してしまう事件が後を絶たないという。
寝ているあいだも気を抜くことが許されないアメリカという国は、やはりどこか致命的に病んでいるのではないか。僕にはそう思えた。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| ジャマ・エル・フナ広場で民族楽器を演奏するグループ。派手な衣装が目を引いた。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
|