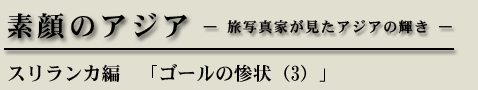|
|
|
|
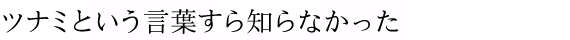 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| カルタラにある寺院の中で、色鮮やかな花を手にした少女に出会った。お参りをするときには、門前の花屋で花を買い、仏像の前に供えるのがスリランカの習慣だ。 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
スリランカは日本のように頻繁に地震が起こる国ではないから、ほとんどのスリランカ人が地震や津波について何の知識も持たないまま被害に遭った。僕はツナミエリアで数多くのスリランカ人と話をしたけれど、「ツナミ」という言葉を事前に知っていたという人は、ガマニさん一人だけだった。
ガマニさんはゴールからバスで一時間ほど東に行ったところにあるウェリガマという町に住む、六十五歳の老人である(六十五歳の誕生日がまさに津波当日だったそうだ)。日本人の感覚だと、六十五歳というのはまだ年寄りと呼ぶには早すぎる年齢だけど、雪のように真っ白い顎髭を伸ばしているガマニさんには、いかにも物知りの長老という雰囲気があった。実際に話してみると、豊富な知識を持つインテリだということがわかった。
「小さい頃から地理が好きでね。いろんな本を読んで勉強したものさ。だからツナミという言葉も知っていたんだ。日本は四つの島からなる国だってことも知っているよ。ホッカイドウ、ホンシュウ、シコク、それと後ひとつは何だっけね・・・・そう、キュウシュウ。これで間違いないね?」
僕がその通りですと頷くと、ガマニさんは得意そうに長い髭を撫でた。
「津波がここを襲ったのは朝の九時半だった。でもインドネシア沖で地震が起きたのは、それより二時間半も前なんだ。あそこにはたくさんの船がいたはずだし、地震の情報は外国からいくらでも入ったはずだ。でも二時間半もの間、誰も何もしなかった。もし事前に知らせることができれば、多くの人は助かったはずだ。そうだろう?」
彼の言う通り、地震発生の直後に津波に襲われたインドネシア近辺とは違って、スリランカやインドの被害は防ごうと思えば防げたはずのものである。日本にあるような先進的な津波予報と告知のシステムを持っていれば、ほとんどの人が安全なところに逃げられただろう。
「でも、政府や気象局の人間が何もしなかったからといって、彼らを責めることはできない。あんなことが起こるなんて、誰も予想できなかったんだ。それにもし、『今から一時間後に高さ四メートルの波が襲ってきますから、すぐに逃げてください』と知らせたところで、それを信じる人間がどれほどいただろうか? 穏やかに晴れた朝に、突然大波がやってくるなんて事をね」
「そうかもしれませんね」
僕は頷いた。この日の海も穏やかだった。僕らはしばらく黙って海の方を眺めた。そこに突如として巨大な波が現れることを想像しながら。
|
 |
 |
 |
|
 |
|
|
|
「今じゃラジオをつければ、一日に何百回も『ツナミ』という言葉を耳にする。新聞はツナミ関係の記事で埋まっている。でもツナミが起こる以前に、ツナミという言葉を使ったアナウンサーは誰もいないんだ。こうなる前に、みんながツナミについてもう少し知っていれば、ここまで被害は大きくならなかったと思うよ」
スリランカの人々は『ツナミ』という言葉が日本語であり、「津」が「harbor」を、「波」が「wave」を表しているということをよく知っていた。おそらくテレビやラジオでそういう説明が何度もされているのだろう。今や『ツナミ』は一種の流行語であり、僕が町を歩いていると「アイ・アム・ツナミ!」と呼びかけられることさえあった。俺は津波を被ったんだ、とアピールしたかったのかもしれない。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| トゥクトゥクドライバーが「俺の車のバックサイドを見てくれよ」と言ってきた。見てみると、幌の部分に「TSUNAMI 2004」とプリントされていた。自虐的ジョークなのか、シリアスなメモリアルなのか、僕には判断ができなかったが、とにかく「ツナミ」が一種の流行語となっていることは間違いなさそうだった。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
「しかし動物たちはツナミなんて言葉を知らなくても、みんなツナミがやってくる直前に海岸から逃げ出したんだ」とガマニさんは続けた。「逃げ遅れて死んだのは人間だけだった。動物には第六感というものが備わっていて、それによって異変を感じ取ることができたのだろう。しかし我々には五感しかないから、ツナミに気が付かなかった。ある年老いた僧侶が私にこんなことを言った。『人は森の中で暮らさなくなった。地面の上に直接眠ることもなくなった。ベッドの上で眠り、夜には火を灯し、自然と離れて生活するようになった。だから第六感を失ったのだ』と」
日本人の僕から見れば、スリランカ人の生活は自然に近いものだと思う。海に出て魚を捕り、椰子の木に登ってココナッツを取って暮らしているのだから。沿岸部から内陸に少し入れば、人がほとんど足を踏み入れないジャングルが広がっている。
しかし海をよく知る漁師達でさえ、事前に海の異変に気が付いて逃げ出した人はいなかった。とてつもない大きな波がやってくるのを実際に目にして、それからようやく逃げ出したが、それでは遅かったのだ。自然と共に暮らす漁師にも津波を予測することができなかったのだとすれば、人間から第六感を奪ったのは都市生活の利便さだけではないということになる。おそらく我々は何万年も前に動物的な勘を失ってしまったのだろう。
しかし人間は動物とは違うやり方で危機を未然に防ぐことができる。その象徴的な例が、ゴールの町から海に突き出たかたちで伸びた城塞都市「フォート」である。フォートはスリランカがヨーロッパ列強の植民地だった時代に築かれた町であり、高さ十メートル近くある壁が町を取り囲んでいたために、津波の被害を全く受けなかったのだ。もちろんこの高い壁は、覇権争いを繰り広げていたヨーロッパ列強にとっての外敵――すなわち他国の軍隊――から町を守るためのものだったのだが、それが結果的に津波という未知の脅威を防いでくれたわけである。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| ゴールのフォートは市街の破壊と混乱と喧噪から切り離された不思議な静寂の中にあった。灯台や時計台やキリスト教会といったコロニアル風の古い西洋建築が立ち並ぶ通りは、行き交う人の姿もまばらだった。もともと生活感が乏しい町なのだが、それにここだけが津波被害を免れたことが加わって、フォートは周囲から明らかに浮いた存在になっていた。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
地震予知や津波警報のシステムも、人間が手に入れた新しい「感覚」である。動物的な勘を失ってしまった人間は、自分たちの周囲に高い壁を張り巡らし、科学的なセンサーを使うことによって、脆弱な肉体を守ってきた。そしてこれからもその方向に進んでいくことになるだろう。我々は未知の危険を察知できない鈍感な動物としての道を歩み始め、もう後戻りできないところまで来てしまったのだ。
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
「日本には『天災は忘れた頃にやってくる』という言葉があるんです」と僕はガマニさんに言った。「次のツナミがやってくるのは、何百年も先のことかもしれない」
「そのときには我々はこの世にはいないし、ツナミのことを覚えている人間は誰もいない。君はそう言いたいんだろう? そしてまた同じことが繰り返される」
「そうならないことを祈ります」
「もちろん私もそうだよ。しかし、そのためにはここで起こったことを次の世代に伝えていく必要がある。それが我々の義務なんだよ」
スリランカを襲った津波は、おそらく数百年、あるいは数千年に一度しか起こらないようなものだった。人の人生はたかだか七、八十年であり、自然災害の気紛れなサイクルの前ではあまりにも短い。だから「忘れない」というのは相当に難しいことだ。
阪神大震災が起こったのはたった十年前で、そのとき僕は神戸市に住んでいたのだけど、地震についての記憶の大半は既に失われてしまっている。いくつかの断片的な光景は覚えている。立ち上る炎と煙を覚えている。月の光が赤かったことを覚えている。きな臭いにおいを覚えている。しかし覚えていることよりも忘れてしまったことの方がずっと多い。
忘れないことは難しい。本当にそう思うのだ。
|
|