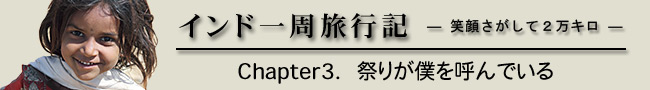|
特定の信仰を持たない僕のような人間にとって、このような「揺るぎなき信仰」は大いなる謎である。彼らが何に熱狂し、どうして自らを痛めつけるのか。その根っこの部分を理解することはできない。
しかしヒンドゥー教徒ではない僕にも、その場を支配する圧倒的なエネルギーを感じることはできた。頭ではなく、皮膚を通した身体感覚として。
祭りの熱気が最高潮に達すると、その場の空気がびりびりと震えるのがわかった。誰かが感じた痛みが、その場に居合わせた人々に次々に伝播し、やがてそれが大きな波となって祭り全体を包んでいくのだ。痛みを媒質にした「場の共振性」。それによって拡散した感情の波は、ふたたび炎の前で踊り狂う男たちの元に凝縮され、激しく渦を巻きながら空へと昇っていくのだった。
単純にすごかった。体の奥が熱くなった。
確かに「意味」を問うなんてナンセンスなのだと思った。
祭りとは考えるのではなく、感じるものなのだ。渦の中に身を委ね、巻き込まれるものなのだ。
|
|