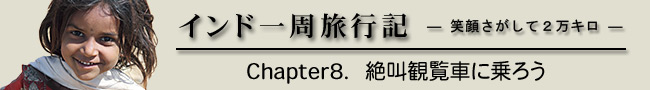|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
インドには「絶叫観覧車」をも上回るアクロバチックな乗り物が存在する。いやぁインドってほんとに広いですね。
それがヒンディー語で「ジュラ」と呼ばれている観覧車である。高さが10メートルほどで、二人がけのゴンドラが8つ付いている小ぶりの観覧車だが、これがなんと人力で動くのである。
ジュラの動かし方は唖然とするほどユニークだった。まず「動力源」となる男たちが、ジュラの骨組みを山猿のようにするすると上っていく。そしてジュラの「軸」の部分に降り、回転する鉄骨の上を「歩く」のである。ちょうどハムスターが回し車の中を走るような要領で、観覧車を回すのだ。
怖くないの?
という素朴は疑問は御法度である。もちろん彼らにも「想像力を遮断するスイッチ」が備わっているのだから、怖いはずがないのである。自分が落ちるなんてことは一切考えない人たちなのだ。
「俺たちはバランスがいいからね。落ちたことは一度もないよ」
と「ジュラ回転人」のサントシュさんは断言する。
ほんまかいな。そう心の中で突っ込みを入れたが、たぶん彼の言うとおりなのだろう。
ちなみにこのジュラの料金は一人10ルピーである。僕も試しに乗ってみたのだが、あの絶叫観覧車のスピード感には及ばないものの、回転はそれなりに速かった。乗り物に弱い人は目を回すだろう。もちろん地元の子供たちは大いにはしゃいでいる。インド人はこういう乗り物にはやたら強いらしい。
僕はゴンドラを降りてからもしばらく「回転人」たちの働きぶりを観察した。彼らはただジュラを回転させるだけでは飽きたらず、自分たちもゴンドラと一緒に回ってみたり、回転するジュラから地面に飛び降りてみたり、反対に動いているジュラへ飛び乗ったりと、まるでサーカス団さながらのアクロバチックな演技を披露してくれた。
この演技を見るだけでもお金を払う価値は十分にあったが、彼らはあくまでも「遊び」としてやっているだけで、お客から喝采を浴びようなどとは夢にも思っていない様子だった。それがまたクールだった。
僕が差し出した10ルピーをサントシュさんは頑として受け取らなかった。遠い異国から来た男が、自分の回す観覧車を楽しんでくれたことで十分に満足しているようだった。
職人気質で紳士的なんだけど、やることはぶっ飛んでいる。なかなか魅力的な人物である。
|
|
|
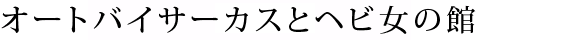 |
|
|
インドを旅するあいだ、僕はいくつかの移動遊園地を訪れてみたのだが、その中で人気実力共に横綱級なのが「オートバイサーカス」だった。これは円筒形の壁の内側をバイクがぐるぐると周回するというアクロバットショーで、スピード感とスリルに溢れた本物の見世物だった。
ショーの主役は例によって事故ることをまったく恐れない「スイッチの切れた」ライダーたち。雷のような轟音をとどろかせながら、猛スピードで壁の内側を駆け上ってくる。彼らの度胸の良さがもっともよく表れていたのが、観客からチップを受ける瞬間である。ハンドルから手を離した状態で、壁の上で待つお客の手から直接お札をひったくっていくのだ。こいつはすげぇ。
大興奮の「オートバイショー」とは反対に、極めつきのチープさで異彩を放っていたのが「ヘビ女の館」である。コブラと女性が合体した奇怪な図柄の看板に誘われておそるおそるテントの中に入ってみたのだが、その中身はひどいの一言だった。
黒服の女が音楽に合わせてダンスを踊っていると、あら不思議、世にも恐ろしいコブラの姿に変身するではありませんか、というのがショーのあらすじなのだが、鏡とライトを使ったトリックは子供だましもいいところで、さすがのインド人も「こりゃないよなぁ」という反応だった。
ヘビ女の顔がはじめから終わりまで能面のように無表情だったのも、冷血動物のヘビを意識しての演技などではなく、単純にやる気がなかったからなのだろう。入場料はたった2ルピー(4円)だったが、それさえも惜しくなるような出来であった。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| これも移動遊園地の出し物のひとつ。有名女優の等身大パネルと一緒に写真を撮れる写真館。料金は20ルピー(40円) |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
移動遊園地に併設されているサーカスも期待通り(?)のチープな代物だった。入場料は15ルピー(30円)と安いのだが、その価値があるかどうかは微妙である。なお、このサーカスの演目については言葉のみの説明になる。テント内部は撮影禁止になっていたからだ。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| サーカスの入り口で背の低いピエロが呼び込みをしていた |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
まず最初に登場したのは、セパレート水着を着た若い女の子。「ヤングマン」のBGMに乗って、体の柔らかさをアピールする。芸自体は中学校の体操部員レベルで、「つかみ」としては少々パンチ不足にも思えたが、それ以上に気になったのは彼女の体型だった。腕にもお腹にも太ももにも肉が付きすぎているのだ。水着の上に腹の贅肉が乗っかっているボンレスハム状態なのである。
トップバッターの看板娘がこんなに太っていていいのだろうか?
そんな疑問が頭をかすめる中、音楽が「ヤングマン」から「ランバダ」に変わった。懐かしさと共に哀愁を誘う選曲である。ラテンの粘っこいリズムに乗って登場したのは、先ほどの太った娘の妹だった。顔も体型もそっくりなボンレスハム姉妹が披露するのは、またしても柔軟体操である。演技内容はともかく、二人の息がまったく合っていないのはどういうわけだろう。ちゃんと練習しているのか?
そのあとボンレス娘はもう一人増え(なんと三姉妹だったのだ)、三人でフラフープの演技を披露した。これはあえて書くほどのものではない。プルプルと震える三つのお腹の上で、グルグルと回る輪っか。ある種のマニアが見れば喜ぶかもしれない。
顔も体型もそっくりのボンレス三姉妹のインパクトがあまりにも強かったから、そのあと出てきた口から火を噴く男や、空中ブランコや、自転車のウィリー走行なんかはあまり記憶に残らなかった。演目が進むにつれて技のレベルが上がっていったし、それなりにスリリングなプログラムだとは思うのだが、全体的に今ひとつ盛り上がりに欠けていた。
問題は演技の未熟さだけでなく、サーカス団員の愛想のなさにもあった。彼らは決められた演目を淡々とこなすだけで、「お客を楽しませよう」という積極的なサービス精神を持ちあわせていなかったのだ。技が決まってもニコリともせず、申し訳程度に片手を挙げるだけ。まるで「笑ったら負けよ」とでも言いたげな態度なのである。
お客の方も同じようにひどかった。難易度の高い技が成功しても拍手は一切起こらないし、歓声やため息が出ることもない。見事なまでに無反応なのだ。唯一お客がわいたシーンは、白い犬が輪っかを飛び越したときだけ。これでは団員がやる気をなくすのも無理はなかった。
サーカスに限らずコンサートでも演劇でも同じだと思うが、ライブというものは観客とパフォーマーが一緒になって作り上げていくものである。
それを反面教師的に教えてくれたのが、インドの盛り上がらないサーカスだった。
|
|
|
|
|
|
|