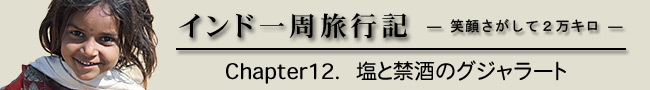|
|
|
 |
 |
 |
 |
ヴェラワルを出てから、海沿いを走る国道8E号をさらに西へと向かった。
国道8Eでは荷車を引いて歩くラクダの姿をよく目にした。ラクダ車はとてもスローな乗り物である。リキシャよりも牛車よりも遅い。人が歩くのとさほど変わらないスピードで、一歩一歩を踏みしめるように歩いている。御者ものんびりしたもので、手綱や鞭も握らずにごろんと横になっている。中には昼寝をしている御者もいる。たとえ居眠り運転をしても、ラクダ車が事故を起こすことはないのだろう。
僕はラクダの人を食ったような顔がすごく好きなのだが、このラクダ車という乗り物も忙しく走り回る現代人に一石を投じているようで(もちろん本人たちにそんな気はないだろうが)、なんだか好感が持てるのである。
そんなに急がなくたって、いつかきっと目的地に着くさ。
ラクダは独特の風貌でそう言っているようだった。
ラクダ車を写真に撮っていると、近くの家に住むおじさんに声を掛けられた。
「まぁお座りなさい」
言われるまま、庭先に置かれたプラスチックの椅子に座り、よく冷えたスプライトをいただいた。カラカラに喉が渇いているときに飲むスプライトより美味いものがあるだろうか。あー、生き返る。
グジャラート州はまだ2月の終わりだというのに、とても暑かった。昼過ぎには40度近くまで気温が上がる。こういうときにはチャイではなく、ソフトドリンクが飲みたくなる。というかチャイなんて熱いうえに甘ったるくて、とても飲めるような状況じゃないのだ。
昔の旅行記には「どれだけ暑くても、インドでは熱いチャイが最高だ」などと書かれていたりするが、今ではインド人も熱いチャイより冷たいソフトドリンクを好むようになっている。昔は選択肢がなかったのだ。チャイしかないから黙ってチャイを飲んでいた。ところが今では田舎にまで電気が行き渡り、冷蔵庫も安く手に入るようになったので、誰もが冷えたコーラやペプシを求めるようになったのである。
もちろん「冬でも夏でもチャイがいいのだ」という人も今もたくさんいて、僕にスプライトをくれた親切なおじさんもその一人だった。彼のチャイの飲み方はちょっと変わっていた。カップに入ったチャイをいったんソーサーにこぼしてから、ソーサーに口をつけてズズーっと飲むのである。
「ここら辺ではみんなこうやるんだ。カップのままだと熱いからね」
おじさんはインド軍の退役軍人なので、片言ながら英語が話せた。僕がバイクでインドを一周していると知ると、
「ラジャスタンにやってきた記念にメヘンディを施してあげよう」と言った。
メヘンディとはヘナという植物の葉の力で一時的に肌を染める化粧法のこと。ラジャスタンの女性たちは結婚式などのおめでたいときには必ずこのメヘンディをするのだそうだ。
メヘンディはヘナの葉を乾燥させて粉末状にしたものに水や油などを加えて作る。ペースト状になったメヘンディをチューブに入れて模様を描き、完全に乾くまで待ってから剥がすと、その部分の肌が赤茶色に染まるという仕組みだ。
僕の腕にメヘンディを施してくれたのはおじさんの娘だった。インドにはプロのメヘンディー・アーティストもいるようだが、友達や家族同士で模様を描き合って楽しむのも一般的だという。娘さんの手際は見事で、下絵もなしに複雑な草木模様を描いていった。体が覚えているのだろう。
|
|
|
「この模様には『あなたの健康と幸せを願う』という意味があるんだ」とおじさんが言った。「メヘンディが守ってくれるから、無事に旅を続けられるよ」
「ありがとうございます。でもメヘンディが消えてしまったら、どうなるんですか? お守りの効果は消えてしまうんでしょうか?」
「心配いらないさ」と彼は笑って答えた。「インドの神様はきっと守ってくれる。でも、なるべくならメヘンディは消さない方がいい」
そう言われたから極力洗わないようにはしていたのだが、残念ながら3日後には色が落ち始め、1週間経った頃にはすっかり模様が消えてしまった。
幸いなことに、そのあと事故に遭うようなことはなかったのだが。
|
|
|
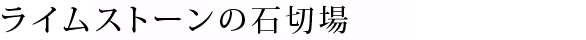 |
|
|
バレージという町の近くには、地面に巨大な穴がいくつも空いているエリアがあった。その穴は一辺が50メートルほどの正方形で、深さは10メートル以上もあり、壁はほぼ垂直に切り立っていた。何かの遺跡(古代のプール?)のようにも見えたが、さほど古いものではなさそうだった。
穴の正体がライムストーン(石灰岩)の石切場だと教えてくれたのは、採掘責任者のメル・ジャレジャさんだった。彼によれば、このあたりでライムストーンの採掘が始まったのは30年ほど前のこと。技術的には簡単で、地面から真下に掘り進むだけなので、土地さえあればどんどん掘れるという。15メートルほどの深さまで掘ると、また別の土地に移って掘る。それを繰り返したせいで、巨大な穴ぼこだらけの景観が生まれたのだ。
ライムストーンは30キロほどの重さのブロックに切り分けて出荷される。卸値は1個あたり15ルピー(30円)。あまり高級な石材ではないらしく、主に家の壁材などに使われているそうだ。
石切場は非常に過酷な仕事場だった。凄まじい勢いで回転する円形カッターは、あたり一面に白い粉塵をまき散らし、それをまともにかぶる労働者はたちまち全身が真っ白になってしまう。それなのに彼らはマスクもゴーグルも着けていないのだ。無茶である。粉塵を日常的に吸い込むことで肺が病気になることを知らないのだろうか。
メル・ジャレジャさんによれば、労働者の日給は12時間働いて200から300ルピーだそうだ。平均の3倍以上にあたる額だが、もしそれが本当だとしても「命を削る」働きに釣り合うとは思えなかった。
|
|