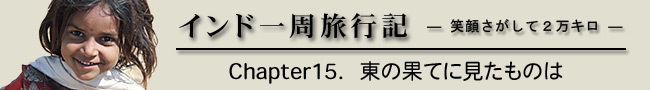|
 |
|
|
 |
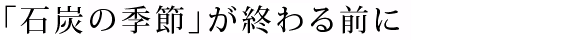 |
 |
 |
ラドルンバイの市場では、二十人ほどの男たちが輪になってサイコロ賭博をやっていた。日本の丁半博打と同じようなもので、ツボ振りがサイコロを二つ振り、客が予想する出目に現金を張る。ユニークなのは使うサイコロが一辺10センチぐらいある巨大なものだということ。そのサイコロを入れるツボも当然のことながら大きくて、水汲みバケツを流用していた。東南アジアでもこれと同じようなサイコロ賭博を見たことがあるのだが、サイコロがこれほど大きい理由はよくわからない。夜の暗闇の中でも見やすくしているのだろうか。
インドで博打を見るのは珍しいので、しばらく輪の外から観察していると、胴元らしき恰幅のいいおっさんがつかつかと近寄ってきた。麻のジャケットに濃い色のサングラス、首には太い金のネックレス。いかにもそっち系のいでたちである。「外国人は出て行け!」とすごまれるのかとも思ったが、そうではなかった。
「あんたはディスカバリーか?」とおっさんは言った。
「・・・ディスカバリー?」
発見? 意味がよくわからなかったが、よくよく聞いてみると「あんたは『ディスカバリー・チャンネル』の取材で来たのか?」と訊きたいのだとわかった。アメリカのTV放送局『ディスカバリー・チャンネル』は質の高い科学番組やドキュメンタリー番組で世界中に知られているが、インドでもケーブルテレビには必ず組み込まれていて人気が高いのである。
「違いますよ。日本から来た旅行者なんです」
僕は正直に答えた。世界中の辺境に取材班を送り込んでいる『ディスカバリー・チャンネル』も、さすがにここには来たことがないだろう。はっきり言って「テレビ的に絵になる」場所ではない。
「そうか。ディスカバリーではないのか」
胴元のおっさんはいかにも残念そうに言った。やくざの親分的な風貌からは想像できないが、意外に知的好奇心が強い人なのかもしれない。
「日本にもこういうギャンブルはあるのか?」
親分は気を取り直して言った。
「ありますよ」
「それは良かった。あんた写真撮りたいんだろう。どんどん撮れよ」
たぶんこういう賭博はインドでも違法だろうから、写真は御法度だろうと思っていたのだが、案外そうでもないらしい。ガンジャと同じように、法律上はダメでも実際に警察が取り締まることはない(もしくは取締りに来ても賄賂を渡せばお咎めなし)ということなのかもしれない。
ツボ振りがサイコロを振る姿を写真に撮り、デジカメのモニターで見せてあげると、集まった男たちは大いに沸いた。特に喜んだのが親分その人で、こわもての顔をくしゃくしゃにして子供のように笑うのだった。そして「これ、取っとけよ」と胸のポケットからお札を取り出して僕に握らせた。真新しい100ルピー札だった。
「こ、こんなものもらえませんよ」
僕は慌てて返そうとしたが、親分は「いいから、いいから」と言って受け取らない。
困ってしまった。インド人から「お金をくれ」と言われることはしょっちゅうあったが、逆に自分がもらうことになるなんて夢にも思わなかったからだ。しかも100ルピーである。インドではちょっとした額だ。博打で儲けている親分にははした金なのかもしれないが、この国には日給が100ルピーにも満たない人が大勢いるのである。丸一日必死で働いてようやく手にできるのが50ルピーか60ルピーという労働者が、おそらく何億人いるのだ。その現実を知っている以上、親分がくれた100ルピーを「はい、そうですか」と言ってそのまま受け取る気にはなれなかった。彼が示してくれた親愛の情は嬉しかったが、それとは別に自分だけがズルをしているような後ろめたさを感じないわけにはいかなかったのだ。
結局、僕はもらった100ルピーをこの町で使い切ることにした。市場の中の食堂でぶっかけ飯を食べたときの代金として20ルピー払い、残りの80ルピーは4人の物乞いに渡した。たまたま僕の手に渡ったお金なのだから、同じようにたまたま出会った人の手に渡せばいいじゃないか。そう思ったのだ。そうして100ルピーがすべてポケットから消えたとき、僕は背負っていた重い荷物を下ろしたときのような深い安堵感を味わったのだった。
昔の西部劇にはゴールドラッシュに沸く町の酒場で酔っぱらった男たちが喧嘩を始める場面が出てきたりするが、ラドルンバイの雰囲気もそれに近いものがあった。
地面を掘るだけで金がもらえるという「うまい話」を聞きつけてはるか遠方から押し押せてきた労働者たちは、常に事故の危険と隣り合わせているからこそ、その日その日を刹那的に生きようとするのだろう。明日は岩盤の下に埋もれているかもしれない。だったら今夜のうちに有り金をぱーっと使い切ってしまおうじゃないか。そんな快楽主義的な気分の横溢が、インド社会の表舞台から締め出されている「飲酒」と「肉食」と「賭け事」を全面的に解放させているのではないか。
実際、この町で財を成したのは「大博打」に勝った者だ、という話を聞いた。ただの森林地帯だった場所を最初に掘り始めた人々は、あらかじめ「ここに石炭が埋まっている」という確かな情報を得ていたわけではなかったようだ。事前のボーリング調査などなしに、いきなり地面を掘ったのである。それで運良く石炭の鉱脈にぶち当たったら大儲けできたし、ハズレだった場合には大損を被って終わった。俗に「山師」なんて言い方があるが、鉱山開発は本当にハイリスク・ハイリターンのギャンブル性の高い投資だったのだ。
ラドルンバイの町から数キロ離れたところにあるルンバイは、石炭で一山当てた人々が住む町である。そこには混沌と喧騒から完全に切り離された清潔な町並みがあった。どの家も明るい色に塗られたコンクリート製の立派な邸宅を構え、大型四輪駆動車を二台か三台所有していた。それは炭鉱労働者たちが住む竹とわらで作った粗末な掘っ立て小屋とはあまりにも違いすぎる世界だった。貧富の差が激しいインドにおいても、「持つ者」と「持たざる者」の違いがこれほどまでに鮮明に表れている土地は珍しかった。
「もちろん俺だってリッチになりたいよ」とトラック運転手のマルシーは言った。「そのためにこうして毎日働いているんだ。でも、もうそろそろ石炭の季節は終わる。雨季になると仕事ができなくなるからね」
農作物ではない石炭に「収穫期」があるとは知らなかった。実はメガラヤ州はモンスーンが直撃することが多いために世界有数の年間降水量を記録する「雨の州」なのだ。日本の約7倍にあたる1万2000ミリもの雨が降るという。そんなわけで雨季になると炭鉱に水がたまって採掘がストップするし、頻繁に起こる土砂崩れによって石炭を運ぶ国道も機能しなってしまうのだ。
実際、僕とマルシーは突然降り出した雨を避けるために入った雑貨屋で立ち話をしていたのだった。かなり強い降りの雨だったが、そのあいだも人夫たちは休むことなく石炭を運んでいた。「石炭の季節」が終わる前にできるだけ稼いでおきたいのだろう。
石炭で黒く汚れた人夫たちの額が、降りしきる雨に濡れて薄い光を放っていた。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|