|
 |
|
|
 |
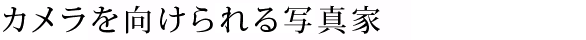 |
 |
|
「ハロー・フレンド!」
ダッカの街を歩いていると、しょっちゅうこんな風に声を掛けられる。
いきなり友達。
まだひとことも言葉を交わしていないのに、なぜか満面の笑みで握手を求められたりするのだ。バングラ人というのはとにかく過剰なほどフレンドリーなのである。花屋のお兄ちゃんが「ウェルカム・バングラデシュ!」と言ってバラの花を一輪プレゼントしてくれることもあったし、市場では売り物のトマトをくれる人もいた。「俺の写真を撮ってくれよ!」とポーズを取る人も珍しくなかった。
彼らは親日家でもある。イスラム国に敵対しているアメリカや、昔から繋がりの深い(それゆえ愛憎も深い)インド、アジアの覇権を握ろうとする中国には辛辣な意見を持つ人も多いが、日本に対して悪い印象を持つ人はほとんどいなかった。長年に渡って道路や橋などのインフラ整備に協力してくれた援助国であり、様々なハイテク製品を輸出する技術立国というポジティブなイメージが浸透しているようだ。
ダッカの旧市街を歩いていると、ひとりの老人が、
「あなたは日本人なのか?」と声を掛けてきた。
「そうですよ」と答えると、
「このプアーなカントリーに来てくれてありがとう!」と笑顔で言うのだった。「ジャパンとバングラデシュはフレンドだからね。君が来てくれて本当に嬉しいよ」
そして友好の証にチャイをご馳走してくれた。
バングラデシュを旅していると、このような無償の親切を何度となく受けることになる。老人の言うとおりバングラデシュはプアーな国だ。けれどホスピタリティーと親切さだけは他のどの国よりもリッチだった。
もちろん、その過剰なまでの親切さは「しつこさ」や「うざったさ」と表裏一体でもある。バングラ人はとても好奇心が強く、フレンドリーで、しかも遠慮がない。いくら「放っておいてくれ」オーラを出していても無駄である。だから、ただ街を歩いているだけで男たちに囲まれて「どこから来た?」とか「名前は何だ?」などと矢継ぎ早に質問されたり、何十人もの暇そうな子供たちが「ハメルンの笛吹き」のように僕の後ろにくっついて歩いてきたりもする。こういうことが毎日続くと、さすがにうんざりしてくるし、ときには「ええ加減にせぇよ!」と叫びたい衝動にも駆られた。
 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
| [動画]ダッカの街を歩いていると、こんな風に男たちに囲まれることがよくある |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
バングラデシュを旅する人は、「動物園のパンダになったみたいだ」と感じることになるだろう。外国人は常に誰かから好奇の目で見られることを覚悟しなければいけない。視線から逃れたくても、隠れる場所はほとんど無い。
だからもう、とことん楽しむしかない。パンダ扱いを受けるのは仕方がないと諦めて、パンダライフをエンジョイする。それができれば、バングラデシュの旅は俄然面白くなってくるのだ。
ダッカではいろんな男に声を掛けられた。すれ違いざまに、
「あんたフォトグラファーなのかい?」と聞かれたこともある。なんの前置きもなく、挨拶も抜きに、いきなりである。
「・・・そうだけど」
相手の前のめりな感じに気圧されながら答えると、彼は訛りの強い英語でさらにたたみかけてきた。
「やっぱりそうか。ずいぶんいいカメラを持っているからな。確かキヤノンとニコンは日本のメーカーだよな。どちらも素晴らしいカメラを作っている。実は俺もフォトグラファーなんだ。パートタイムだけど新聞記者をしている。それでだね、今から俺の言うことをぜひ日本人に伝えて欲しいんだ。『バングラデシュはたくさんの貧しい人々と一握りの金持ちでできている』。わかったかい?」
「・・・わ、わかったよ」
これだけの長ゼリフをほとんど一息で話しきってしまう肺活量に圧倒されている僕を尻目に、彼はあっという間に雑踏の中に消えていった。僕の反応なんて聞きたくもない、という感じで。自分の言いたいことだけを言い、それが終わるとさっさと去っていく。相手の話をよく聞かないバングラ人は多いが、ここまで一方的に自分の話だけする人はさすがに珍しかった。
この自称ジャーナリスト氏以上に不思議だったが、ダッカ駅近くの住宅街で出会った「ゴキブリ男」である。
その若者は水が入ったガラスのコップを大事そうに持って歩いていたのだが、僕を見つけると嬉しそうに「ほら、中を覗いてみろよ」と言った。で、言われたとおり覗いてみると、そこには黒々とした大きなゴキブリが2匹入っていたのである。どちらもまだ生きていて、水面を必死で泳いでいる。
嫌がらせなのか?
一瞬そう思ったのだが、彼は終始にこやかで、その表情からは悪意のカケラも感じられない。ふざけている様子もなかった。大事に育てているペットを見せたがっている人みたいなのだ。
彼は真顔で続けた。
「これ気に入った? 飲む?」
ゴキブリを、飲む? なんで?
「いや俺はいいよ。あんたが先に飲めよ」とかわすと、
「いやいや、そう言わず、あんたが先に飲みなって」
とコップをぐいと突きつけてくるのだった。
「どないせいっちゅうんや!」
さすがにそう突っ込まざるを得なかった。まったくわけがわからなかった。
やっぱり嫌がらせだったんだろうか。それとも中2レベルの悪ふざけなのか。いずれにしても、冗談はもうちょっとそれらしい顔で行ってほしい。いやほんとに。
街を歩いている僕を写真に撮ろうとする人も増えた。これまでは「ハロー」と声を掛けてきたり、握手を求めてきたりするだけだったのが、「あ、ガイジンだ。ちょっと撮らせてよ」って感じでカメラ付きの携帯を取り出す人が増えたのである。僕は写真家なので人にカメラを向けるのには慣れているのだが、カメラを向けられるのはあまり得意ではない。どんな顔をしてレンズを見たらいいのかわからなくなってしまうのだ。にっこりと笑えばいいのだろうか。それとも肩を組んで「チェキ!」ってやればいいのだろうか。
バングラデシュでも携帯電話の普及は急ピッチで進んでいる。すでに人口の半分近くが携帯を手にしているという統計もある。中国製のシンプルな携帯電話なら1000円以下で買えるし、通話料も1分あたり1円以下という安さだ。これなら国民の大部分を占める農民にも十分に払える。リキシャ引きが携帯で喋りながらペダルを漕いでいたり、農村で収穫をするおばさんがポケットから携帯を取り出したり。10年前には到底考えられなかった光景が現実になりつつあった。
もちろんカメラ付き携帯はまだ高級品で、そこそこの収入がないと買えないが、町工場でシャツを真っ黒にして働くあんちゃんが持っているぐらいだから、かなり大衆化しているとも言えそうだった。
中には僕が食堂でカレーを食べている様子を、隣の席から動画で撮影する人もいて、これには苦笑せざるを得なかった。「オレにプライバシーはないのか!」と声を荒げるつもりはないけれど、「ガイジンが飯食っている動画」なんて撮って一体どうするんだろうと首をかしげてしまった。
家族や友達に見せるんだろうか?
それともYouTubeに投稿するんだろうか?
|
|
|
|
|
|
|
