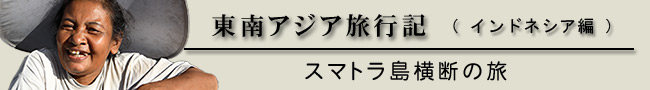|
 |
|
|
 |
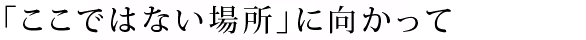 |
 |
 |
メダンで中古バイクを手に入れると、さっそくスマトラ島西部アチェ州に向けて出発した。
予定は特に決めなかった。とにかく走れるところまで走って、日が落ちる前に適当な宿を見つけて泊まる。基本的には毎日がその繰り返しだった。天候や道路のコンディションが良ければ一日に300キロ以上進めることもあったが、雨にたたられて100キロも進めない日もあった。しかしいずれにしても自分が常に「ここではない場所」に向かっているという現在進行形の感覚は、バイク旅行でしか味わえない特別なものだった。
宿探しにはいつも苦労した。州都などの大きな町に行けば、安宿から中級宿まで選択肢も豊富にあるし、宿にあぶれる心配はまずないのだが、山奥にある小さな町に行ってしまえば宿が一、二軒しかないようなところも多かったのだ。
そこそこ清潔で、窓があって、夜に本が読める程度の明るい電球がついていて、便所の臭いがこもらない部屋、というのが僕のささやかな――本当にささやかな――希望だったのだが、それが全て満たされることはほとんどなかった。それどころか、たいていの場合僕の希望とは正反対の(つまり汚くて、窓がなくて、暗くて、便所の臭いがする)宿を選ばざるを得なかったのである。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| スマトラ島の典型的な安宿の一室。通常、バイクは駐輪場やフロントロビーで保管してもらうのだが、この宿では自分の部屋で一緒に泊まるように言われた。盗まれたら一大事というのはわかるのだが、どう考えても奇妙な光景ではあった。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
しかし観光地でもないローカルな町を旅する限り、それは仕方のないことだった。たとえそれがどんなに硬くても寝るためのベッドがあり、たとえそれがどんなに薄汚れていても体を洗うための水場がある。スマトラ島の田舎町では、そのことに感謝しなければいけないのだ。
メダンを出発して二日目、僕はイディという小さな町で宿を探すことにした。まず市場の近くでたむろしている「ベチャ」(バイクにサイドカーを付けた簡易タクシー)の運転手たちに「この町に宿はある?」と訊ねてみた。ベチャ乗りならこの町の事情に詳しいだろうと思ったのだ。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| ベチャの運転手たちは市場の近くにたむろしていることが多い。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
この町には宿がひとつしかないらしく、ベチャ乗りたちは一斉に同じ方角を指した。しかし、どこまで行ってもそれらしき建物が見当たらない。「ホテル」や「ウィスマ」や「ロスメン」(どれも宿を表すインドネシア語)という看板が見当たらないのである。
変だなぁと思いながらウロウロしていると、近所のおじさんが「あんたどこ行くの?」と聞いてきた。
「このあたりに宿があるって聞いたんですけど・・・」
僕がそう答えると、おじさんは「それだったらここだ」と目の前の建物を指さした。それは何の変哲もないただの民家だった。とりたてて大きくもないし、宿を表す看板もない。しかしおじさんは確信を持って「ここだ」と言い張るのである。
地元の人がそう言うのなら、ここが宿屋なのだろう。そう思ってドアをノックしてみた。しかし反応がない。仕方なくドアを開けて「パルミシー(すみませーん)」と呼びかけてみた。居間のテレビはつけっぱなしになっていたが、人の気配はなかった。僕はもう一度声を出した。
「パルミシー! 誰かいませんかー?」
するとようやく奥の部屋から、太ったおばさんがぬっと顔を出した。派手な色のノースリーブのワンピースからは、棍棒のような腕と丸太のような足がつきだしている。昼寝から起きたばかりなのだろう、眠そうな顔で頭をぼりぼりと掻きながらのしのしと歩いてきた。
「あの・・・ここってロスメンですか?」
「ロスメン・・・そう、ロスメンだよ」
「ここに寝られるんですよね?」
僕は身振りを交えて訊ねた。頭を横に倒して、右手を添える。世界共通のボディーランゲージである。
「ああ。あんた一人?」
おばさんは怪訝そうな顔の前に、指を一本立てた。僕は頷いた。一人だったら泊めてもらえないのだろうかとも思ったが、そういうことではなかった。ついて来なさいと言うと、おばさんはすたすたと先に行ってしまった。僕は慌てて玄関でサンダルを脱ぎ、おばさんの後を追った。
居間を抜けると、洗濯物がたくさん干された小さな中庭があり、その奥に泊まり客用の部屋があった。おそらく僕のような客がやってくると、家の中の余っている部屋を解放して使わせているのだろう。文字通りの「民宿」である。
部屋には小さなベッドがふたつと机と扇風機があった。一応必要最小限のものは揃っている。掃除も行き届いている。悪くない。おばさんに宿代を訊ねると、四万ルピア(五百円)ということだった。高くもないし安くもない、リーズナブルな価格である。
「ダリ・マナ?(どこから来たの?)」
僕から受け取ったお金を数え終えると、おばさんが訊ねた。そして冬眠明けのクマのような大きなあくびをした。
「サヤ・オラン・ジパン(私は日本人です)」
と僕は答えた。この辺の自己紹介文は一日に何度もやり取りするので、すぐに覚えてしまった。私は日本人で、メダンからバイクに乗って来ました。
「ジパン! あんた日本から来たの?」
眠そうな目をしていたおばさんの表情が、そのひとことで一変した。こんな辺鄙な町の安宿に日本人が泊まりに来るなんて、まずあり得ないことなのだろう。
「あんた、ほんとに日本人なのかい? だってさ、日本人は肌が白くて、背が低いじゃないか。でも、あんたはそうじゃない。どうしてだい?」
おばさんは英語が全くわからないので、身振りなどから推測するしかなかったのだが、彼女が言わんとしていたのは、このようなことだったと思う。肌の白さはともかく、なぜか多くのインドネシア人が「日本人は背が低い」と思い込んでいるのは不思議だった。平均身長で比べるなら、インドネシア人の方が日本人よりも低いはずなのだ。あるいは、第二次大戦中にこの地にやってきた日本軍の兵士はみんな背が低かったのだろうか。
僕が日本人の平均よりもいくらか背が高い理由を説明するのは難しかったが(そんなの日本語でも説明できないが)、肌の白さを証明するのは簡単だった。Tシャツの袖をまくり上げればいいのである。
「これが元々の肌の色なんです。ね、白いでしょう? インドネシアの強い太陽で、腕や顔が焼けて黒くなったんですよ」
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| 陽気で太っていて声が大きいのが、典型的なインドネシアのおばさんだ。 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
この時はまだインドネシアに来て三日目だったから、正確には僕の日焼けの半分以上はその前に旅していたカンボジアの太陽のせいである。しかしそんな細かいことをいちいち説明する必要はないだろう。とにかく、それでおばさんの疑念は晴れたようだった。
おばさんは名前をアニといった。そして、この看板のない宿にも一応「ロスメン・アダム」という名前が付いていることがわかった。アニさんは最初は極端に無愛想だったが、僕が遠方からやって来た旅行者だと知ると、興奮した口調でいろんなことを話し始めた。もちろん僕にはほとんど理解できなかったが、そんなことは気にしない。いたってマイペースなのである。僕が何とかわかったのは、13歳になる娘の名前がカリスマだということだけだった。
僕はアニおばさんが入れてくれたコーヒーを飲みながら、彼女の話に適当な相づちを打ち続けた。インドネシアのコーヒーは砂糖がたっぷり入っていて甘ったるいのだが、疲れた体にはそれくらいがちょうど良かった。サニさんの話はいつ果てるともなく続いた。おばさんという人種がお喋り好きなのは世界共通なんだなぁとしみじみ思った。
やがて相づちを打つのにも疲れてくると、僕は頬杖をついて目を閉じた。意味不明な外国語にじっと耳を傾けていると、人は睡魔に襲われるようだった。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|