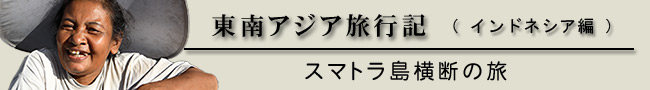|
 |
|
|
 |
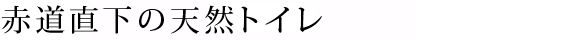 |
 |
 |
赤道を越えたのは、午後2時を少し過ぎた頃だったと思う。「と思う」と書かなければいけないのは、どこが赤道なのかよくわからなかったからだ。赤道を示す看板やモニュメントがないかと注意深く観察しながらバイクを走らせていたのだが、それらしきものはどこにもなかったのである。
もし道路の上に赤いラインでも引いてあったら、右足を北半球に左足を南半球に置いてベタな記念写真でも撮ってやろうと考えていたのだが、それも叶わぬ夢となってしまった。赤道がどこを通っているかなんて、地元の人にはどうでもいいことなのだろう。国境線や州境などと違って、それを越えたからといって具体的に何かが変わるわけではないのだ。
南半球に入って最初に訪れた町がサッサだった。海岸線に沿って広がる漁師町で、長い砂浜に小さな漁船がいくつも並び、椰子の木陰で男たちが漁網を編む姿があった。
サッサの町で知り合ったのがジョニスさんだった。彼は若い頃に外国人相手のガイドの仕事をしていたらしく、インドネシア人には珍しく流暢な英語を話した。僕はいい機会だと思って、次の目的地パダンまでの道のりを訊ねることにした。地図によれば、海岸線に沿った道を100キロあまり南下すればパダンに着くはずなのだが、肝心の道路がどこにも見当たらなかったのだ。
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| 漁網を補修する男。朝のひと仕事が終わると、漁村はのんびりとした空気に包まれる。 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
「海沿いをバイクで走るつもりだって? そりゃ無理だよ」とジョニスさんは断言した。
「どうしてですか?」
「海岸線には道と呼べるようなものはない。4WDなら砂浜を走ることもできるが、バイクじゃとても無理だよ」
「でもこの地図には州道が通っていることになっているんですけどね」
ジョニスさんは僕が持っていた地図を覗き込むと、笑い声を上げた。
「この地図、間違ってるね。こんな道はどこにも存在しないよ」
「本当ですか?」
「本当だよ。なんなら今から見に行くかい?」
確かにこの地図には細かい間違いがたくさんあった。町の名前が間違っていたり、あるはずの町が抜け落ちていたり。その程度のミスであればまだ許せるのだが、今回のようにありもしない道路が堂々と描かれているというのは、いくら何でもひどすぎる。ロードマップとして致命的ではないか。僕がそう憤慨すると、ジョニスさんは「まぁそう言いなさんな」と肩を叩いた。
「この地図はインドネシアで買ったんだろう? だったら仕方ないさ。インドネシア人は誰も地図なんて使わないからな。道に迷ったら人に聞けばいいと思っているんだ。でも地図が間違っていたからこそ、君はこの町に来れたんじゃないか。サッサはいいところだ。ゆっくりしていけばいい。泊まるところ? 心配はいらないさ。俺の家に泊まればいい」
そんなわけで、僕はこの赤道直下の町サッサで一夜を明かすことになったのである。不正確な地図と親切な男のおかげだった。
|
|
|
夕食はジョニスさんの家でご馳走になった。小魚をカリカリになるまで油で揚げたものと、野菜の入ったスープとご飯。シンプルな献立だった。ちなみにジョニスさんは唐辛子を栽培する農家なので、さぞかし辛い味付けなのだろうと半分怯えながら口に運んだのだが、意外にあっさりしていておいしかった。
夕食を食べ終えると、ジョニスさんと連れ立って町を散歩した。夜の町は昼間よりもずっと賑わっていた。赤道直下に住む人は暑い昼間を避けて夜行性になるようだ。
僕らは雑貨屋に集まっているおじさんたちと世間話をしたり、テレビの歌謡ショーを眺めているおばさんたちと一緒にお茶を飲んだりした。誰もが顔見知りの小さな漁師町にふらりとやってきた異邦人は、行く先々で質問攻めにあった。最も多かったのは「あんたはどうしてこの町に来たのか?」という質問で、これには「地図が間違っていたからだ」と答えるしかなかった。ジョニスさんが僕の英語をインドネシア語に訳して伝えると、「なんだそういうことだったのか」と笑いが起こった。
「こうやってみんなと一緒に夜を過ごすのが、何よりの楽しみなんだよ」とジョニスさんは言う。「話題? たいしたことじゃないさ。今日の出来事や、他愛もない冗談とかだね」
今ご近所の話題の中心は、一週間後に迫ったジョニスさんの妹の結婚式のこと。彼の実家はその準備に大忙しだった。この町に住むミナンカバウ族は母系社会の伝統を維持していることで知られている。ここでは一族の実権は父親ではなくて母親の方にあり、だから結婚式も新婦の実家で挙げることになっているのだそうだ。
珍しく星がきれいな夜だった。雨季のスマトラ島では夜になると分厚い雲が空を覆い、空にぴったりと蓋をしてしまうことが多いのだが、この日はいつになく雲が少なかったのだ。空の中心に位置しているのはオリオン座だった。こんなに高い位置にオリオン座があることに驚いたのだが、日本とは緯度が違うのだからそれも当然なのだろう。
「サザンクロス(南十字星)はどれですか?」と僕はジョニスさんに訊ねた。
「サザンクロス? さぁ知らないなぁ」と彼は言った。「俺は星については詳しくないんだ。星っていうのはとても遠くにあるんだろう? インドネシアと日本では見える星が違うのかい? それは知らなかったなぁ・・・」
赤道直下の空には日本では見ることもできない星もたくさんあるのだろうが、ジョニスさんも僕も天文にあまり詳しくないので、結局はわからずじまいだった。
翌朝は夜明けと共に目を覚ました。さっそく浜辺に向かったが、すでに何隻もの漁船が沖に向けて出発した後だった。地引き網を引っ張る漁師たちの姿もあった。漁師町の朝は早い。夜明け直後がもっとも忙しい時間帯なのだ。
僕は砂浜を歩き回りながら、働く男たちの姿を写真に収めた。波はとても穏やかで、潮の匂いを含んだ風もすがすがしかったが、波打ち際に動物の糞らしきものがいくつか転がっているのが気になった。
最初は家畜の糞なのだろうと思っていた。しかし牛の糞にしては小さすぎるし、山羊の糞にしては大きすぎる。色といい形といい大きさといい、どうも僕らが普段「見慣れたモノ」であるような気がしてきた。
この糞の正体が明らかになったのは、お尻を剥き出しにしてしゃがんでいる男の姿を目にしたときだった。しかもそんなあられもない格好の男が立て続けに三人も並んでいたのである。間違いない。波打ち際に転がっていたのは漁師たちのウンコだったのである。
漁師たちは海を眺めながら悠々と用を足していた。煙草を吸っている人もいたし、隣の男と世間話をしている人もいた。もちろん下半身は丸見えなのだが、それをあえて隠そうとする人はいなかった。この格好が恥ずかしいという意識はないのだろう。
カニが砂浜に掘った縦穴に自分のウンコを落とすという、実に器用な真似をする男もいた。遊び心なのかは何なのか目的はよくわからないのだが、巣穴で眠っているカニからすれば迷惑この上ない話である。もし僕がカニだったら男のお尻めがけてハサミを突き立ててやるんだけど。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| 牛がとぼとぼと歩く砂浜の上で、一人の男が用を足していた。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
用を足し終わった男たちはそのまま海の中にちゃぷちゃぷと入り、左手でお尻を洗った。トイレットペーパーもいらないし、塩水で洗うのだからお尻だって清潔である。波打ち際に置き去りにされたウンコも、やがて波によって海に運ばれていく。まさに「天然の水洗トイレ」だ。
砂浜に置き去りにされたウンコは打ち寄せる波によって海に運ばれ、プランクトンによって分解され、食物連鎖を経て魚を育てる。漁師たちはその魚を捕まえて食べ、それが再びウンコとなって海に運ばれる。砂浜の天然トイレはこのような大きな循環の中にあった。それは日本人が慣れ親しんでいるシステマチックな清潔さとは正反対のものだった。この町ではウンコは処理されるべき「汚物」ではなく、人の体から出て自然に還っていくごく当たり前のものとして存在していた。
ジョニスさんによれば、この町で家の中にトイレがあるのは全体の1割ほどで、住民の9割は外で用を足しているという。目の前にいつでも使える天然トイレがあるのに、どうしてわざわざ家の中に狭苦しいトイレを作らなければいけないのか。そう考えている人が多いのだろう。
もちろん人前で堂々とお尻を出すのは男性だけで、女性たちは近くの茂みに隠れてこっそりと用を足している。なんだか不公平な気がするが、ここでは昔からずっとそうなのだという。
確かに、波打ち際で煙草を吹かしながらのんびりと用を足している男たちは、一切のストレスから解放されたような表情をしていた。ひょっとしたら天然トイレには露天風呂と同じようにリラックスさせる効果があるのかもしれない。
サッサの住人たちが陽気で開けっぴろな性格なのも、ひょっとしたら「天然トイレ」のせいなのかもしれない。この町ではどの家の扉も開け放たれ、自由に出入りすることができた。人々はプライバシーの確保にはあまり関心がないようだった。浜辺でお尻まで丸出しにしているのだから、他に隠すものなど無いのだろう。
そのような町で、人々は海の恵みに寄り添って生きていた。漁師たちは涼しい朝のうちに仕事を終えてしまうと、あとは家の中で昼寝をしたりカードゲームをしたりしてのんびりと過ごす。余分な獲物を捕らえるために無理をして船を出す人はいない。大漁の日もあれば不漁が続くときもあるが、自然とはそういうものだとどこかで達観しているのだった。
決して豊かとは言えないが、十分に満ち足りている。サッサにあるのはそんな暮らしだった。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|