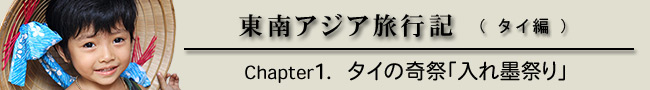|
|
|
 |
 |
 |
 |
タイに世にも奇妙な祭りがあると聞いて、アメリカ人のウィリアムと共に取材に向かったのは2006年3月のことだった。バンコクから車で1時間ほど離れたところにある「ワット・バンプラー」というお寺で、その祭りは行われていた。正式名称は「ワイ・クル」。英語名はタトゥー・フェスティバル。入れ墨祭りである。
ワイ・クルは地元の人のあいだでは大変有名なイベントなのだが、これまで外国人にはほとんど知られていなかった。というのも、この祭りの開催日は直前になるまで公にされないからだ。僕らは八方手を尽くしてなんとかその情報を手に入れ、祭りの前日に会場に向かった。寺の担当者に「前夜祭から見学した方が面白いよ」と勧められたからだ。
僕らはバンプラー寺院の奥にある静かな僧院に向かった。ここで夜を徹して入れ墨を彫っていると聞いたからだ。この寺院には入れ墨を彫る技術を持った僧がたくさんいて、祭りの前夜になると、地元の男たちが入れ墨を彫ってもらうために集まってくるという。
僕らが僧院に入ったときには、すでに50人以上もの男たちが入れ墨の順番を待っており、部屋の中は男たちの発する熱気で蒸し暑かった。一目で堅気ではないとわかるヤクザ風の男もいたし、屈強な体を持つ現役のムエタイ選手もいたが、大半はごく普通の外見の男たちだった。タイでは日本のように入れ墨に対する抵抗感は少なく、願いを叶えるための願掛けの意味で入れ墨を彫る人も多いという。中には「耳なし芳一」みたいに顔以外のありとあらゆる部分に隙間なく入れ墨を施している男もいて、これはかなりおっかなかった。
入れ墨の図案は仏教やヒンドゥー教の神々や動物たちを題材にしたものが多い。ハヌマーン(猿の神様)やガネーシャ(象の神様)、刀を手にした阿修羅などがよく掘られているという。ここで掘られているのは僧侶の手による「真面目な」入れ墨であって、欧米人が好むファッション・タトゥーとは全然別物なのだ。
「ワイ・クルの前夜に彫られた入れ墨には、特別な力が宿る」
と教えてくれたのは、この祭りを仕切っている顔役の男だった。彼は流暢に英語を話すインテリであり、物腰も穏やかなのだが、周囲の人間を無言で従わせるような威圧感も持ちあわせていた。筋骨隆々の大男でさえ、彼の前では小さくなっている。その威圧感の源は大きな背中に掘られた虎の入れ墨にあった。
「どうして虎なのかって? それは虎の入れ墨を彫ることで、私の体に虎の力が宿るからだ。私は毎年祭りの前夜に虎をひとつ彫ってもらう。つまりこの背中には十数年分の虎の力が宿っていることになる。だから私は『虎将軍』と呼ばれるようになった」
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| これは「タイガーテンプル」で飼われている虎。まだかわいい子供である。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
この「虎将軍」氏は元警察官であり、最近までかなり高い役職に就いていたのだそうだ。退職してからも、地域の顔役として一目置かれる存在であるらしい。しかし全身に虎の入れ墨を施して、周囲ににらみを利かせる虎将軍は、元警察官というよりもヤクザの親分といった方がぴったりくるように思えた。
もっとも、タイ警察とタイ・マフィアは上の方で繋がっているという噂もあるから、僕が虎将軍から受けた印象はそのまま彼の実像にあてはまるのかもしれない。
入れ墨に使われている道具は伝統的なものだった。僧侶は柄の長い千枚通しのような道具を握り締め、その刃先を青い墨に浸してから、男の肌に打ち込んでいく。ミシンのように速くて正確な動きだ。ひとつの図案を彫り上げるのに要する時間は5分から10分ほど。順番待ちの男がずらりと並んでいるので、手際よくこなさないととてもさばききれないのだ。
入れ墨を掘られているあいだ、男たちはひとことも言葉を発しない。呻き声を上げることすらない。奥歯を食いしばり、かたく目を閉じて、ひたすら痛みに耐えている。しかしその痛みが尋常ではないことは、額に浮き出てくる玉のような汗を見ていれば明らかだった。
入れ墨が終わった瞬間に、一種のトランス状態に陥る男もいた。白目をむき、息づかいが獣のように荒くなり、甲高い奇声を上げ、正気を失って暴れ出すのである。これが激しい傷みによってもたらされる肉体的なリアクションなのか、それとも虎将軍が言うように「特別な力が宿った」結果なのかはよくわからない。しかしフィジカルなものであれスピリチュアルなものであれ、この夜に行われる入れ墨には特別な意味がある(と男たちが考えている)のは確かだった。
ウィリアムは最初からここで入れ墨を彫ってもらうつもりだったのだが、あまりにも旧式な現場を見て、その決心が揺らいでいた。入れ墨に使う道具はどれもまともに消毒されているようには見えなかったし、それで何十人もの男の体に次々と入れ墨を彫っていくのだから、感染症の危険も十分に考えられた。
しかし結局、彼は彫ることを選んだ。「もし感染症が発生していたら、こんなイベントを毎年続けられるわけがない。だから安全だ」という論法だった。確かにその通りだ。虎将軍のように十年以上も通っている人がたくさんいるのだから、おそらく安全なのだろう。
ウィリアムを決断させたのは好奇心だった。彼は何ごとにおいてもまず自分で経験してみないと気が済まない男なのである。
ウィリアムはLAでの快適な生活を捨ててアジアを長く放浪し、日本に渡って英語教師の職を得た。日本人と結婚し、二人の息子が生まれた。しかし安定した「勤め人」としての人生に彼は馴染めなかった。そして「自分の力で新しいウェブマガジンを立ち上げよう!」と決意する。世界各地を旅し、現地の人々や旅行者へインタビューを行って、日本人に「生きた英語」を学べる場を提供しよう。それが彼のプロジェクトのコンセプトだった。
そのコンテンツ作りのために、僕は彼に協力することにした。そして二人でタイを旅することになったのである。
ウィリアムが右腕に彫ることにしたのはヒンドゥー教の象の神様「ガネーシャ」だった。彼は以前からガネーシャが好きで、自分の守り神にしたいと思っていたという。
僧侶が「針」を右腕に打ち始めると、ウィリアムは目を閉じて大きく深呼吸を始めた。もちろん彼も呻き声を漏らすことはなかった。歯を食いしばって、激しい痛みをなんとかなだめようとしていた。右手をぐっと握り締め、全身の筋肉に力を込める。額に玉のような汗がいくつも浮かび、それが頬を伝って流れ落ちていった。
「40年生きてきたけど、こんなに痛い思いをしたのは初めてだ」
長い十分間が終わって目を開けた彼は、開口一番そう言った。
「あの痛みを言葉にするのは難しいな。刺すような、焼けるような痛みなんだ。呼吸に意識を集中させることで、なんとか耐えることができた。でも本当にタフだったよ」
|
|
|
「次はお前が彫るのか?」
と僧侶から訊かれたのは、そんなウィリアムの偽らざる感想を聞いた直後だった。ロッククライミングが趣味のマッチョな肉体の持ち主ウィリアムでさえ、「生まれて初めての痛さだ」と言っているのだ。普通に考えれば即座に「ノー」と言うべきところだろう。そもそも僕には入れ墨に対する興味なんてまるでないのだから。
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| まさに「耳なし芳一」状態。よくもまぁこんなに掘ったものだ。 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
でも僕は迷っていた。それは純粋な好奇心ではなく、その場の雰囲気に飲まれていた結果なのだと思う。何しろこの場にいる数十人の男の中で、体に入れ墨がないのは僕一人なのである。ここでは入れ墨がない方が特殊であり、異端なのだ。
ここにいる男たちは同じ痛みを共有することによって連帯感を強めていた。苦痛に耐え、呻き声を我慢することで、自分が「男」であることを証明する。その寡黙で密やかな絆に対する憧れが、僕の中にも生まれていたのである。
でも結局、僕は首を縦に振らなかった。ありていに言えばびびったのだ。激しい苦痛を受け入れるだけの心の準備ができていなかったのである。
その夜は僧院の中で入れ墨の男たちと一緒に雑魚寝した。何体もの仏像が鎮座する部屋の床に、ごろんと横になって眠ったのだ。石の床の上はひんやりとしていて気持ち良かったが、僕の隣で眠っていた二匹の犬が大きなイビキをかくのには参った。犬のイビキというものを聞いたのはこれが初めてだった。
|
|
|
|
|
|
|
|