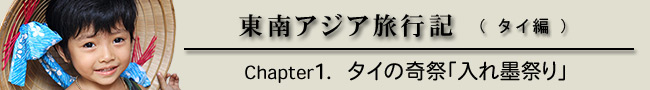|
 |
|
|
 |
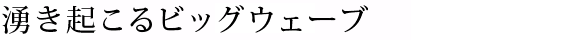 |
 |
 |
入れ墨祭りは開始から2時間半ほど続いたが、その中で何度か「ビッグウェーブ」が起こった。通常、男たちがトランス状態に入るタイミングは各自バラバラなのだが、この「ビッグウェーブ」の間だけは、何十人も男たちが連鎖反応を起こすように一斉にトランス状態に入るのである。
それは凄まじい光景だった。会場のあちこちで「ウォー!」「ウォー!」という雄叫びが上がり、狂った形相の男たちが次から次へと仏像めがけて走りだすのだ。この時ばかりは兵士たちも必死だった。体を張って突進を受け止め、耳を引っ張って正気に戻し、またすぐに別の男の突進を止める。仏像の周辺には雄叫びと怒号と土煙が充満し、戦国時代の合戦場のような修羅場になっていた。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| ビッグウェーブが起こると、何十人もの男たちが一斉にトランス状態に入る。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| かつてのオウム信者のようにあぐらをかいたままぴょんぴょん跳ねる男もいた。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
僕も必死だった。いつもならファインダーを覗き込んで、その中に写る被写体に意識を集中させていればいいのだが、この「ビッグウェーブ」のあいだは右からも左からもトランス状態の男が突進してくるので、少しでも油断すると彼らに突き飛ばされかねなかったのだ。
突き飛ばされるぐらいならまだいいが、カメラやレンズを壊されたら大変である。だから僕は常に周囲に目を配り、衝突の危険を回避しながら、同時に被写体にもできるだけ近づこうと動き回った。それはスリリングなゲームだった。僕は男たちの熱狂と興奮に共鳴しながらも、一方でそれを冷静に観察していた。僕の体にもトランス状態の男たちと同じようにアドレナリンが湧いていたが、それに完全に身を委ねるわけにはいかなかったのである。
僕らは祭りが終わる直前に会場を抜け出して、タクシーを捕まえた。祭りの参加者は1万人近くに達していたので、混雑に巻き込まれる前に帰るのが得策だと思ったのだ。
タクシーに乗り込むと、僕らは二人して大きなため息をついた。そしてどちらからともなく笑い始めた。何がおかしいのか自分でもよくわからなかったが、一度笑い出すともう止まらなかった。ウィリアムは僕の肩をポンポンと叩き、腹を抱えて大笑いした。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| 変身した男の表情の恐ろしさに思わずのけぞる女の子。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
取材している間は、僕らも真剣そのものだった。生半可な気持ちで向かい合えるような相手ではなかった。男たちの少なくとも一部は、本気で狂っていた。彼らは入れ墨を通して神や仏や精霊たちと交信し、そのエネルギーを目一杯発散させていた。それを信じるか信じないかは別として、あの場を支配していたのは紛れもなくスーパーナチュラルな力だった。
しかし彼らが真剣であればあるほど、ある種のおかしみも増幅されていった。なぜ虎になるのか。なぜ仏像を目指すのか。なぜ兵士に止められるとすごすごと帰るのか。全ては謎であり、理屈では説明不能なハイパーな現象だった。そしてその現象から距離を置いて第三者的な視点から眺めてみると、すべてが壮大なコメディーショーのように思えてくるのだった。
僕らを乗せたタクシーはハイウェーをひた走り、40分ほどでバンコク市内に戻ってきた。高層ビル群と広告看板が建ち並ぶ、見慣れた都市の風景だった。
「僕らはどこにいたんだろう?」
ウィリアムは窓の外を眺めながら呟いた。
「ものすごく遠い世界から帰ってきた気分だね」と僕は頷いた。
「まったく、あんなにクレイジーな祭りは見たことがないよ」
「ところで、君の体には象の魂は降りてこなかったの?」
僕はウィリアムの右腕を指さして言った。そこには昨日彫ったばかりの象の神様の入れ墨があった。
「そうみたいだね。信仰が足りなかったのかもしれない」
「もし君が象に変身しても、僕がすぐに耳を引っ張ってやるから大丈夫だよ」
「そうなったときはよろしく頼むよ」
こうして僕らの長い一日は、ようやく終わったのだった。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|