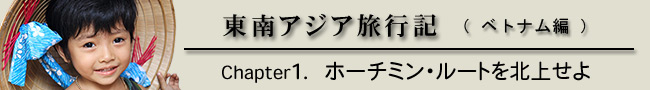|
|
|
 |
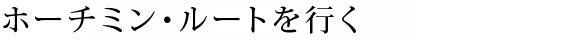 |
 |
 |
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| ラオスとの国境近くの山岳少数民族が住む集落で籠を使って魚をとる子供たち。 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
ホーチミン市でバイクを借りると、さっそくその日から北に向かって走り始めた。当面の目的地は1900キロ彼方にある首都ハノイである。
ホーチミン市・ハノイ間を陸路で移動する場合には、海岸線に近い国道1号線に沿ったルートを通るのが一般的だ。フエ、ダナン、ホイアン、ニャチャンといった都市や観光名所は、全て国道1号線沿いに集中しているからだ。
しかし僕はこの国道1号線ではなく、「ホーチミン・ルート」と呼ばれるラオス国境近くの辺境を通る幹線道路を北上することにした。ベトナムを一周することになった以上、同じ道を往復してもつまらないと思ったからだ。
このホーチミン・ルートはベトナム戦争当時、南ベトナム解放民族戦線(通称ベトコン)が作った秘密の補給路が原形になっている。アメリカ軍の偵察機に見つからないようにわざわざ森の中を切り開いて作ったルートだけに、相当に辺鄙なところばかりを通る道である。
当時、工事は困難を極めたという。兵士たちは峻険な山をスコップで削り、深いジャングルをナタ一本で切り開き、増水した川に木組みの橋を架けながら、地道に道を作っていった。爆撃や作業中の事故によって多くの命が失われたが、彼らは決して諦めなかった。
今のホーチミン・ルートには、そのような過酷な歴史の面影は残っていない。水牛の背にまたがって田んぼを横切る子供たちや、すげ笠を被ってお茶の葉を摘む女たち。そんな当たり前の笑顔に出会える平和な道になっている。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| ホーチミン・ルートはアップダウンの多い山道だった。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
一日の走行距離は250キロほど。これは僕にとってかなりのハイペースだった。のんびりと周囲の景色を眺めながらバイクを走らせ、何か面白いものを見つけたら止まって写真を撮るというのがいつもの旅のスタイルなのだが、それを貫くにはベトナムはあまりにも長すぎたのである。走っても走っても、なかなか先が見えてこないのだ。
一日の大半をバイクに座って過ごす僕にとって最大の悩みがお尻の痛みだった。幸いにして痔にはならなかったが、最後までヒリヒリとしたお尻の痛みを耐えながら旅を続けることになった。英語にはネタを足で稼ぐという意味の「レッグワーク」という言葉があるけれど、その表現を借りるなら、この旅はネタを尻で稼ぐ「ヒップワーク」であった。
お尻の痛みはあったものの、ホーチミン・ルートをバイクで走ること自体はとても楽しかった。路面の状態は予想以上に良かったし、交通量も少ないのでバイクの流れを読むことに神経を使う必要もなかったからだ。大きくうねる山道を、自分が走りたいように自由に走る。爽やかな風と一体になって、急な坂道を駆け上ったり下ったり。ジェットコースターのような爽快感を味わえる道だった。
ホーチミン・ルート沿いの景色はいわゆる「ベトナムらしい風景」とはずいぶんかけ離れていた。茶色く濁った大河も、緑が一面に広がる肥沃な田んぼもなく、赤茶けた土と深い森が大地を覆い尽くしていたのだ。ベトナム中部の高原地帯にはコーヒー農園とサトウキビ畑が多かった。「クーサン」と呼ばれるキャッサバ畑も目についた。キャッサバは根から良質のデンプンがとれ、家畜の飼料にもなる。乾燥に強く、痩せた土地でも育つので、政府が積極的に増産に乗り出しているという。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| キャッサバの皮を剥いていた女たち。最近では、キャッサバからとれるデンプンからバイオ燃料を作る試みも始まっている。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
コントゥムという町の近くでは、天然ゴムの木から樹液を採集している人々がいた。彼らは特殊な刃先のカマを使って、木の幹に螺旋状の切り込みを入れていた。こうして幹に傷をつけておくと、じわじわと白い樹液が染み出してくる。それを集めたものがゴムの原料になるわけだ。
「ここに住んでいるのは主に少数民族の人たちなんです」
流暢な英語で説明してくれたのは、作業を指導しているクウェンという名前の若い女性だった。華奢なフレームの眼鏡をかけた頭の回転の速そうな女の子だ。クウェン曰く、少数民族の人々はもともと焼き畑農業で自給自足的な生活を送っていたのだが、ゴム農園やキャッサバ畑で働いて現金収入を得る道を選ぶ人も増えているのだそうだ。
24歳のクウェンはホーチミン市の農業大学を出てすぐにこの地に赴任してきた。今はルームメイトと二人で部屋を借りて暮らしている。家族と会えないのは寂しいが、なるべく彼女の方からは電話を掛けないようにしている。声を聞いたら余計寂しくなるからだ。
「私の家族はみんなバラバラに住んでいるんです」とクウェンは言う。「お父さんはホーチミン市近郊で魚の養殖をしているし、お母さんはニャチャンの実家で魚を売っています。弟はフランスに留学しているし、妹はフエの大学に通っています。だから家族が揃うのは、年に一度のテト(旧正月)の時だけなんです」
クウェンが一番心配しているのは母親だった。以前から病気がちだったのだが、最近は特に体調が良くないという。本来なら自分がそばにいて看病するべきなのだが、今は仕事があるのでここを離れられない。
「私はこの仕事にやりがいを感じています。貧しい少数民族の人を豊かできるから。でも夜一人でお母さんのことを考えていると、自然と涙が出てきてしまうんです」
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| 田植え前の田んぼを耕すのは水牛の重要な仕事だ。ひと仕事終えた水牛が、主人に引っ張られて家路に就く。 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
ホーチミンのような風貌の老人を轢きそうになったのは、ラオス国境にほど近いクアンナム省の山道を走っているときのこと。その老人は白く長いヒゲをあごに蓄え、深緑色のニット帽を被っていた。かなり高齢なのだろう。腰は90度近く曲がっていたのだが、足取りはやけに軽やかだった。老人はスタスタと早足で道路に飛び出してくると、いきなり僕のバイクを通せんぼするように両手を広げた。
「ちょっと、ちょっと! 危ないじゃないですか!」
慌てて急ブレーキをかけてなんとか事なきを得た僕は、ヘルメットのバイザーを上げて文句を言った。しかし老人は意に介す気配もなく、ニコニコと笑いながら僕の背後に回り込むと、バイクの後部座席にひょいとまたがってしまった。どうやら彼はヒッチハイクをするために僕のバイクを止めたらしい。なんとも強引な人である。
「おじいちゃん、どこまで行きたいの?」
一応英語で訊ねてはみたものの、もちろん老人には伝わらなかった。ただニコニコと首を振るばかりである。この人だって、まさか外国人が運転するバイクを止めることになるとは思っていなかったのだろう。
「まったく、しょうがないなぁ・・・」
こうして僕は行き先もよくわからないまま、老人を乗っけてバイクをスタートさせた。
実はこのあたりではヒッチハイクは珍しいことではない。公共バスも一応は走っているのだが、人口密度の低い地域なので使い勝手は悪いし、かといって自転車で走れるほど平坦ではないので、住民は必然的にバイクに頼らざるを得ないのである。自分のバイクを持っていない人は、他人のバイクに便乗するしかないのだ。
|
|
|
この人もベトナム戦争を戦ったのだろうか。この道の建設にも関わったのだろうか。背後でのんびりと煙草を吹かせている老人に聞きたいことはたくさんあったのだが、言葉が通じないので諦めるしかなかった。
20分ほど走り続けたところで、老人は僕の肩をポンポンと叩いた。「降ろしてくれ」という合図なのだろう。僕がバイクを止めると、彼はよっこらしょと座席から降り、歯のほとんど抜け落ちた皺だらけの口で、「カムオン(ありがとう)」と言った。去っていく足取りはやはり軽快だった。
それ以後もヒッチハイクに応じたことは何度かあったのだが、いずれも「お一人様限定」で二人以上は乗せなかった。一度、おじさん一人を乗せようとしたら、後から芋づる式に奥さんと子供も乗り込んできて、「それは無理だよー」と頭を抱えてしまったことがあったからだ。重量オーバーで走るのに慣れたベトナム人にとっては、4人乗りなんて朝飯前なのかもしれないが、素人の僕にはとても真似できない芸当だったのである。
|
|