 |
|
|
 |
 |
 |
|
ラジャスタンの砂漠地帯を抜けてパンジャブ州に入ると、空気の質ががらりと変わった。
きりりと澄み渡った高い空には薄い雲が幾筋も伸び、透明で硬質な光がすべてのものの輪郭を鋭く際立たせていた。


風は乾いていた。アフガニスタンやトルコと同じ匂いがした。少し埃を含んだ大陸の匂いだった。
そう、ここパンジャブは西方のイスラム世界へ向かう玄関口なのだ。
インド随一の穀倉地帯であるパンジャブ州は、緑色の州だ。だだっ広い小麦畑の緑と、マスタード畑の黄色い花が交互に並び、用水路を流れる透明な水がそのあいだを満たしている。目が覚めるような鮮やかな景色だった。


小麦畑の緑の絨毯を抜けると、小さな村が現れる。村の中心にはシク教の白い寺院があり、その隣には小学校がある。寺院の前の広場では、ターバンを巻いた老人たちが日向ぼっこに興じている。高いレンガの壁で覆われた農家には、山羊や牛がたくさん飼われている。家の外には牛糞を積み上げた小山がある。これを乾かして燃料にするのだ。
パンジャブ州を旅するあいだ、僕は何十回も「あれ? さっきここを通ったよな」と思った。パンジャブ州の農村の風景は、判で押したように同じパターンの繰り返しだったからだ。集落は2,3キロおきにほぼ等間隔で連なっていて、そのあいだを小麦畑とマスタードと水路が埋めている。どの村もまったく同じだった。この既視感は、パンジャブ州の田園風景が自然にできたものではなく、運河の建設によって計画的に造られたものであることを示唆していた。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| 色とりどりのターバンを巻いた男たちが、ときには牛車に乗り、ときにはリキシャを漕ぎながら、村と村を繋ぐ細い道を行き来している。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|

もともとパンジャブ州もラジャスタン州と同じように乾いた不毛の土地だった。それを変えたのが灌漑事業だった。インダス川の支流に巨大なダムを作り、そこに貯めた水を運河によって下流の農地に行き渡らせようという一大プロジェクトが、当時の首相ネルーの元で実行に移されたのだ。住民たちもこの事業に惜しみない労力を注ぎ、やがてパンジャブ州はインド有数の穀倉地帯と呼ばれるまでになったのである。
|
|
|
 |
|
|
パンジャブ州でカメラを向けたのは男性ばかりだった。色とりどりのターバンを頭に巻き、ヒゲを長く伸ばしたシク教徒の男たちは、実にカッコ良く、絵になる被写体だったからだ。彼らはみな顔の彫りが深く、背も高く、胸板も厚かった。硬派でマッチョ。「男が惚れる」タイプの男たちだった。
シク教徒の男たちには威厳と近寄りがたさがあったから、カメラを向けるときには緊張した。しかし実際に話してみると、彼らはとても優しく、写真に対してもおおらかだった。外見からは想像できないほど、気さくで親切な男たちだったのである。カメラを向けると「フォトかい。いいよ、撮りなよ」と胸を反らせてポーズを取ってくれた。その姿をモニターで見せると、「よく写ってるじゃないか!」と無邪気に顔をほころばせるのだった。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| 一見怖そうに見えるシク教徒の男たちは意外に気さくだった。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
バティンダという町の商店街を歩いているときに声を掛けてきたスクインダールさんは、身長190cm近い大男だった。彼もまた写真に対して積極的な男で、頼んでもいないのに「俺の写真を撮れよ」と言って、カメラの前で妙なポーズを取った。その姿をモニターで見せてあげると、例によって子供みたいに大喜びして、チャイとお菓子をご馳走してくれた。
スクインダールさんは警察官だった。ただの警官ではなく、警察学校で教鞭を執る先生だという。それなのに、彼は酔っぱらっていた。目は血走り、吐く息にはアルコール臭が混じっていた。まだ午後5時である。今日は非番なのだろうと思っていると、
「いや、今も仕事中だよ」と何でもない顔をして言うのだった。
おい、こんなことでいいのか、パンジャブ警察。と思ったが、もちろん口には出さなかった。
確かにパンジャブは酒に寛容な州である。町中には酒屋やバーも多い。しかしさすがに現役の警察官が勤務中に酔っぱらっているのはマズいんじゃないだろうか。
「俺はいくら飲んでも酔わない質なんだ。今も全然酔っぱらっちゃいない」
彼はそう言い訳すると、鼻歌交じりに雑踏の中に消えていった。左右に大きくふらつく足どりは、酔っぱらい以外の何者でもなかった。
県のホッケーチームのコーチをしているというスクデブさんも大変親切な人で、僕を自宅に招いてチャイをふるまってくれた。ホッケーはインドの国技であり、クリケットに次いで人気のあるスポーツだ。世界大会でも好成績を収めていて、世界ランクは7位。インドでは数少ない「国際競争力のある」競技だと言っていいだろう。プレーヤーにパンジャブ人が多いのも特徴だという。
「ホッケーはとてもスピーディーなスポーツなんだ」と彼は言った。「攻守の切り替えも速くて、エキサイティングだ。そこがクリケットとの違いだよ」
「じゃあどうして、クリケットの方が人気があるんですか?」
「あぁ、あの退屈なクリケット」彼は大きく首を振った。「インドには暇な人間が多いのさ。1試合に3日間かかろうとも、ずっと見ていられるんだ。他の国じゃ、こうはいかない。クリケット選手を悪く言うつもりはないよ。彼らは全力でプレーしている。世界的なプレーヤーも多い。でもね、仕事そっちのけでクリケット観戦に熱中している人を、私はどうしても理解できない。彼らにはもっと他にやることがあるはずだよ」
正論である。インドのクリケット人気はすさまじく、特にテストマッチ(国際試合)ともなると、町の電気屋に置かれたテレビの前にたくさんの男が群がることになる。その熱狂が2,3時間で終わるならともかく、3日間も続くのである。「どんだけ暇やねん!」と突っ込みたくなる人がいても不思議ではない。
スクデブさんの人生はホッケーと共にあった。若い頃は全国レベルの選手として活躍し、引退後はコーチの仕事をしていた。しかし58歳になる来年には、コーチ業からも身を引く予定だという。そのあとは友人とビジネスを始めるのだそうだ。
「私はアクティブであることが好きなんだ。やるべきことを全力でやっていると、年は取らないものだよ。コーチとして若者と接しているのも、気持ちを若々しく保つためにはいいことだよ。君のような旅人から話を聞くのも好きだ。とてもいい刺激になるからね」
別れ際には、握手だけでなく、胸と胸を合わせてしっかりと抱き合った。初めて会った人間に対する挨拶にしてはやり過ぎのような気もしたが、これがパンジャブ流なのである。
パンジャブの男たちは過剰なほど親切で、友情に篤く、いかつい外見とは裏腹の無邪気さを持っていた。それはパキスタンやイラン、アラブ諸国の男たちとよく似ていた。やはりここは西方のイスラム文化圏への入り口なのである。
|
|
|
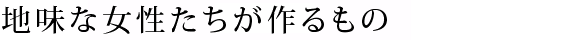 |
|
|
ターバン姿の男たちを撮りまくっていたのとは対照的に、パンジャブ州では女性をほとんど撮らなかった。不思議なことに、男が「俺を撮れよ」と言うところほど、女が撮りにくいという傾向があるのだ。その代表格がイスラム国である。パキスタンやアフガニスタンやモロッコといったイスラム色が強い国では、女性を撮るのがとても難しかったのだ。
そういった国々ほどではなかったが、パンジャブ州の女性たちの反応はあまり芳しくなかった。写真に撮られるのが絶対にダメというわけでもないが、友好的でもない。目に見えない壁のようなものが感じられたのだ。
シク教徒の女性たちが地味だったのも、あまりカメラを向けなかった理由のひとつだった。パンジャブの女性はサリー姿ではなく、サルワール・カミーズと呼ばれるゆったりとした上着ともんぺ状のズボンというスタイルだったので、どことなく垢抜けない印象だったのだ。
そんなパンジャブ女性がよく作っていたのが、牛の糞にワラを混ぜて円盤状に固めた燃料だった。この牛糞燃料はインド各地で使われているものだが、パンジャブ州ではとりわけよく見かけた。それは他の州に比べて開墾が進み、薪の供給が不十分だからだろう。
もちろん地元の人たちにとって、牛糞は汚いものではない。乾いてしまえば匂いはほとんどしないし、火力も強く、長期間保存もできるので、燃料としてとても優秀なのである。
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| 牛糞燃料は生活に欠かせない。これだけ集まると壮観だ。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
