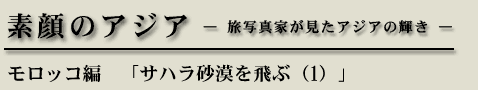|
 |
|
|
|
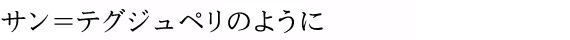 |
|
 |
|
|
 |
僕が2001年にユーラシア大陸一周の旅をしたとき、ずっとバックパックの中に入れていた本がある。「星の王子様」で有名なフランス人作家サン=テグジュペリが書いた「人間の土地」だ。
「人間の土地」は、サン=テグジュペリが郵便飛行機のパイロットとして世界中を飛び回っていた1920年代頃のエピソードを綴ったノンフィクションである。その中でも多くの頁を割いているのが、モロッコ西部のサハラ砂漠の飛行場で過ごした日々だった。
サン=テグジュペリが生きた時代、空と砂漠は常に死の危険をはらんだ場所だった。信頼性の低い飛行機はしょっちゅう故障を起こして墜落したし、運良く砂漠に不時着できたとしても、いつ助けがやってくるかわからなかったのである。
実際、「人間の土地」にはサン=テグジュペリ自身がリビア砂漠で遭難したときの体験が克明に綴られている。救助を求めて砂漠を何日も歩き続けた彼は、極度の乾きと疲労に襲われ、幻覚を見るまでに衰弱していく。読み進めるうちに、こちらまでが喉に激しい渇きを感じ、舌が固まってくるほどの真に迫った描写に、僕は圧倒された。そこには体験した者にしか書けないリアリティーがあった。
20世紀前半には、まだ人類未踏のフロンティアが残されていた。それは飛行機が飛び始めたばかりの空の世界であり、一部の遊牧民のみが行き来する砂漠だった。そのフロンティア開拓の先頭に立ち、さらにそれを言葉に変えていたのが、当時のサン=テグジュペリだったのだ。
サハラ砂漠の入り口にある町メルズーガを訪れたときに、サン=テグジュペリのようにサハラ砂漠の上空を自由に飛べるという話を聞きつけた。二人乗りの超軽量飛行機を使って遊覧飛行を行っている会社があるらしい。当初の予定には全くなかったのだが、こんなチャンスは滅多にないだろうということで、僕らも空を飛んでみることにした。
僕らがコンタクトを取ったのは、ポルトガル人のパイロットが半年前に立ち上げたばかりの会社だった。名前はずばり「デザート・フライ」。このパイロット氏は元々カメラマンをしていたのだが、仕事でサハラ砂漠を訪れたときにその魅力に取り憑かれてしまい、砂漠を飛ぶ遊覧飛行をビジネスにすることを思い立ったのだそうだ。
サハラ上空を軽量飛行機で定期的に飛行しているのは、今のところ彼らだけらしいのだが、初めての試みだっただけに、商売を始めるまでには相当な苦労があったという。
最も大変だったのは、モロッコ政府の役人にビジネスプランを認めてもらうことだった。どこの国でも同じかもしれないが、役人というのは新しいものをなかなか認めたがらないものなのだ。煩雑な書類のやり取りがあったうえに、途中で書類が紛失するというトラブルもあり、何ヶ月もの時間が無駄に流れた末、ようやくプロジェクトが軌道に乗ったのが数ヶ月前のこと。軌道に乗ったとはいっても、まだほとんどの旅行者は彼らの存在を知らないし、風が強い日には飛べないという軽量飛行機の特性もあって、経営は安定していないという。
幸いにして、僕が飛んだ日は風が穏やかだったのだが、こういう日には稼げるだけ稼ごうということで、パイロット氏は休む間もなく空と飛行場を往復していた。
ちなみにサハラ上空を飛ぶのに最も相応しい季節は冬なのだそうだ。上空はかなり冷え込むけれど、空気が澄んでいるので、砂丘が一際美しく見えるという。僕らがここを訪れたのは春だったのだが、風で巻き上げられた埃が空気中に漂っているせいで、残念ながら砂丘はそれほどクリアーには見えなかった。
僕らは朝一番の7時半に飛ぶことになった。飛行場はメルズーガの町から車で10分ほど走った砂漠の中にあった。飛行場と言っても、砂漠の一角を平らにならしただけの簡易的なものだ。滑走路の広さはサッカーのピッチを縦にふたつ繋げたぐらい。超軽量飛行機は離着陸にそれほど長い距離を必要としないのである。滑走路のそばには、大型無線機とレーダーを搭載した四輪駆動車が止まっている。それが管制塔の代わりになるらしい。
パイロット氏は俳優のトミー・リー・ジョーンズに似たおじさんである。背は低いものの骨太のがっちりとした体格で、握手した手には厚みがある。僕はパイロット氏から渡されたヘルメットと分厚いジャケットを着て、後部席に座った。そして三点式のベルトで体をしっかりと固定する。パイロット氏が「さぁ行くぜ」という顔で後ろを振り返り、親指を立てる。僕が「オーケー」と頷くと、背中にある扇風機のお化けのようなプロペラエンジンがバリバリバリという大きな音を立てて回転を始める。
離陸の際の加速はジェット機のそれとは比較にならないほど遅いが、座席が剥き出しだからスリルは十分にあった。飛行機は滑走路の真ん中あたりでふわりと浮き上がって、そのまま左へ大きく旋回した。
僕らはまず飛行場の正面にある大砂丘を目指した。朝日を受けてオレンジ色に輝く砂丘は、圧倒的なスケールと神秘性を帯びていた。風紋が砂丘の表面にリズミカルな模様を刻み、全体を俯瞰してみるとダイナミックなうねりが連続している。まるで北斎が描いた荒波のようだ。このような雄大な景色が風の力だけで作られたというのは、驚き以外のなにものでもない。僕はしばらく写真を撮るという自分の仕事も忘れて、呆然と砂丘を見つめていた。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| 超軽量飛行機からサハラを見下ろす。砂丘の上には観光客がつけた足跡が点々と連なっていた。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
大砂丘を飛び越えたところに広がっていたのは、白い砂漠と黒い砂漠だった。白い砂漠は塩を吹いた土地であり、黒い砂漠は小さな石が一面に散らばった荒れ地である。お馴染みの黄色い砂丘地帯だけではなく、あまりフォトジェニックではない塩の砂漠や石ころだらけの砂漠も、サハラをかたちづくる上で欠かせない要素なのだ。
砂漠を飛んだ後は、高度を下げてオアシスの町の上空を旋回した。ナツメヤシの木々に囲まれた緑の畑があり、その周りに高い壁を持つ家が点々と並んでいる。家の中庭に洗濯物を干している女の姿が見える。男に率いられたラクダの一隊が、茫漠とした荒野を一直線に歩いている。砂漠の圧倒的な広さに比べると、人の営みはとてもささやかなものであり、愛おしいものだった。
飛行機が元の滑走路へ戻ってきたのは、離陸から30分後のことだった。今まで一度も事故は起きていないと胸を張るだけあって、スムーズなランディングだった。
サハラ上空を飛ぶことは予想した以上に刺激的な体験だった。けれど、それと同時に強いフラストレーションも感じた。当然といえば当然なのだが、乗客は座席に固定されたまま上空を移動するだけなのである。僕が右を指させば、パイロットは右に旋回してくれる。高度を下げてくれと伝えれば、すぐに降下してくれる。でも自分で操縦桿を握っているわけではない。決して「自由に空を飛んでいる」わけではないのだ。バイクの後ろに乗っているのと、自ら運転するのとでは気分が全く違うように、自分で操縦桿を握って空を飛ぶ気分は全く別物だろう。飛行の興奮が冷めやらぬ頭で、僕はそんなことを考えていた。
サン=テグジュペリは自由に空を飛び回りたいという夢のために、郵便飛行機パイロットという危険な職業を選んだ。おそらくこのポルトガル人のパイロットがこの商売を始めたのも、サン=テグジュペリと同じような動機だったのではないだろうか。
今の時代に郵便飛行機パイロットは必要ないし、大陸間を無着陸で飛行する冒険飛行の意味も失われてしまったけれど、手付かずの空を自由に飛び回りたいというロマンチックな夢は、形を変えながら別の人間に受け継がれているのだ。
新しいことを始めるのには、常にリスクがつきまとう。それを覚悟の上で一歩を踏み出せる人間だけが、自由に空を飛ぶことを許されるのだろう。
|
 |
|
|