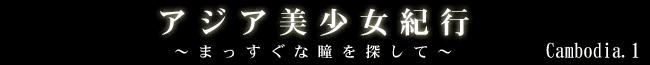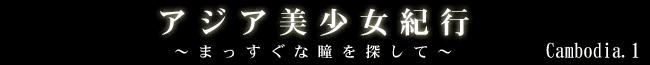|
 |
|
|
|
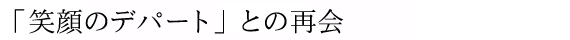 |
|
 |
レアはとにかく表情豊かな少女だった。上半身裸で痩せっぽちの女の子が、マジシャンがシルクハットから沢山の国旗を引っ張り出すみたいに、次から次へといろんな笑顔を見せてくれると、思わずこちらの顔もほころんでしまった。笑顔のデパート。そんな形容詞がぴったりだな、と僕は思った。
最初にレアと出会ったのは2001年初めのことだった。カンボジアの農村でたまたま立ち寄った結婚披露宴に飛び入りで参加したことがあったのだが、その飲めや踊れやの宴会で大いに盛り上がる大人達を不思議そうな顔で眺めていた女の子がレアだったのだ。
カンボジアの結婚披露宴は、日本のように形式張らない――言い換えれば、ずいぶんいいかげんな――ものだった。結婚披露宴というものの真の目的が「飲んで食って騒ぐこと」にあるとは言っても、日本人であれば然るべき形式というものに少しはこだわる。親戚の長ったらしい挨拶があり、キャンドルサービスが行われ、誰かがカラオケで「乾杯」系ソングを歌い、最後には両親への花束の贈呈がある。でも、カンボジアの披露宴にはそのような「予定の流れ」というものが全くなかった。
僕らが飲んだり食ったりしている間、誰一人挨拶に立つ人はいなかったし、場を取り仕切る司会者らしき人物も見当たらなかった。一応「お色直し」はあって、新婦は一度退場し、ピンクのドレスから青いレースのドレスに着替えてくるのだが、新婦の再登場にも拍手すら起こらなかった。みんな飲んだり食べたりするのに忙しくて、新婦の方なんて全然見ていないのである。
宴会の席で振る舞われていたのは「ビールのスプライト割り」という奇妙な飲み物だった。どのテーブルにもビール瓶とスプライトのペットボトルが二本セットで置いてあり、僕がビールだけを注ごうとすると、隣の女の子がスプライトをどぼどぼと注ぎ足してくれるのである。もちろん嫌がらせではなく、「好意」としての行為である。冷蔵庫なんてどこにもない土地で、ぬるいビールを飲むためにこういう飲み方を編み出したのかもしれないが、味の方はひどかった。ビールの苦みとスプライトの甘みが渾然一体となった、予想通りのマズさだった。それでも「郷に入っては郷に従え」の精神で、我慢して飲み続けた。
料理の方はなかなか豪勢だった。野菜入りビーフンから始まり、牛肉の炒め物、骨付きチキンの甘辛煮、豚肉と野菜の炒め物などが、次から次に運ばれてきた。どれも特別に手の込んだ料理というわけではないけれど、普段はあまり食べられない肉類をこの日だけは目一杯食べようという晴れがましさが伝わってくるメニューだった。
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
|
| カンボジアでよく食べられているココナッツ仕立ての麺 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
骨付きのチキンがテーブルに運ばれてくると、その匂いを嗅ぎ付けた野良犬がどこからともなく集まってきた。カンボジアではいたるところにぐたーっと昼寝をしている野良犬の姿があるのだが、村中に漂う肉料理の匂いは彼らの目を覚まさせる効果もあったようだ。
もっとも、野良犬が何匹集まろうとも、彼らに肉を分けてあげようという親切な人間は一人もいなかった。その代わりに人々は食べ残した骨をぽいぽいと地面に投げ捨てていくのだが、犬たちはそれを美味しそうにゴリゴリと噛み砕いて、文字通り跡形もなく平らげていくのだった。普段ろくなものを食べていない彼らにとっては、残り物の鳥の骨も大ご馳走であり、披露宴は残飯処理係としての野良犬の本分を遺憾なく発揮できる場なのである。
宴会の開始から二時間。並べられた料理が全て食べ尽くされてしまうと、庭に並んだテーブルが片づけられ、人の輪ができた。そして大型のスピーカーからアップテンポのダンスミュージックが流れ始めた。飲んで食った後は、当然踊るというわけだ。
一緒に踊ろうや、と僕の手を引っ張ったのは、真っ黒に日焼けした陽気なおじさんである。出来れば酒臭いおっさんじゃなくて若い女の子と踊りたいところだったが、彼の満面の笑顔を前にするとイヤとは言えなかった。おじさんの知っている英語は「ノープロブレム」「オーケー」「アイムソーリー」の三つだけなのだが、それでも何となく意志が通じてしまうのは、お互いに酒が入っているからでもあるのだろう。もちろん踊り出してしまえば、言葉が通じないことなんて全く問題じゃなくなってしまう。
「ノープロブレム」のおじさんは僕の向かい側に立って、ツイストみたいな妙なステップで踊り始めた。仕方がないから僕も彼の真似をして、手を振り、腰を振る。すると周りで見ている女達が大口を開けて笑い出す。僕は決してリズム感が悪い方ではない(少なくとも自分ではそう思っている)のだが、それでも僕とおじさんのダブル・ツイストがよほど可笑しかったのか、女達の笑い声はどんどん大きくなっていった。
ダンスタイムは一時間ほど続いたが、その間僕は休むことなく踊り続けた。正確に言えば、休むことを許されなかったのだ。踊り疲れて休もうとすると、たちまち「ノープロブレム」のおじさんに見つかって、踊りの輪の中に引き戻されてしまうのである。そんなわけで、宴会が終わる頃には全身汗だくになってしまった。
飲んで踊って騒いで、とにかく楽しい宴会だった。はっきり言って新郎新婦なんてそっちのけだったが、そのいい加減さが面白かった。それは僕にとって初めて経験する「旅先での温かい歓待」だったから、なおさらこの出来事が忘れがたいものになったのだった。
|
 |
|
 |
|
|
「あのウェディング・パーティーは本当に面白かったわ」
とモムは懐かしそうに言った。彼女は偶然通りかかった僕を結婚披露宴に引っ張り込んでくれた張本人であり、「笑顔のデパート」レアの姉でもあった。最初の出会いから三年ぶりにモムの家を訪ねてみたのだが、彼女はあの日の出来事をよく覚えていた。でも残念なことに、妹のレアは僕のことをすっかり忘れていた。
「三年前、この子はまだ六歳だったから・・・」
モムは申し訳なさそうに言った。
「それはいいんだよ」僕は首を振った。「僕だって旅先で出会った人全員を覚えている訳じゃないからね。レアのようにはっきりと覚えている子の方が珍しいぐらいなんだ。だからレアが僕のことを覚えていないのも無理はないよ」
九歳になったレアはより女の子らしい顔立ちに変わっていたが、それでもとびきり大きな瞳と艶やかな黒い髪の毛は三年前と全く同じだった。レアは女ばかり四人姉妹の末っ子なので、両親からも姉たちからもかわいがられていて、のびのび育っているという印象を受けた。
「この子は絵を描くことのが何よりも好きなの。将来は学校の先生になりたいんだって。学校の成績だって悪くないのよ」
モムはそう言って妹の頭を優しく撫でた。レアはなんだか照れ臭そうに下を向いていた。
|
|
|
|