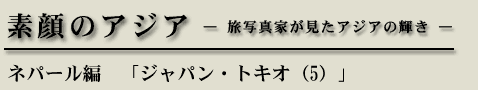|
|
|
|
 |
|
 |
ゴリゴリゴリという重みのある音で目が覚めた。ベッドが震動でガタガタと揺れていた。そのとき僕は嫌な夢を見ていた。どんな夢なのか思い出すだけでも嫌になるような類の夢だ。だからその震動が現実のものなのか、夢の続きなのか、目覚めた直後には判断がつかなかった。
ゴリゴリゴリ・・・。石臼だ。誰かが石臼を回しているのだ。石臼で挽かれているのは白い骨だ。白髪の老婆が真っ白い人骨を臼で挽いているのだ。そこまで考えたところで、僕はようやく本当に目を覚ました。
誰かが石臼を回しているのは現実だったが、もちろん人骨ではないだろう。骨の部分は悪夢の続きだ。誰が人骨を粉になんてするものか。
枕元に置かれた腕時計のグローを光らせると、「AM4:05」の文字が浮かび上がった。もちろんまだ太陽は昇っておらず、あたりは漆黒の闇に包まれている。
僕はベッドから起き上がって、壁の隙間から外の様子をうかがった。そこにはランプの光を頼りにして石臼を回す女の姿があった。石臼の真ん中にはヘソのような穴が空いていて、女はそこにトウモロコシの粒をそろそろと流し込んでいた。
やっぱり骨じゃない。そのことにほっとしたものの、なぜ彼女がこんな早朝(というか夜中)にトウモロコシを挽かなければいけないのか、僕には理解できなかった。早く起きろという合図なのか、あるいは外国人に対する手の込んだ嫌がらせなのだろうか。そんな疑問が頭をよぎった。
石臼はどの農家にも必ずひとつ置かれている必需品である。トウモロコシや豆を粉にしたり、スパイスを挽いたりするときに使われる。普通、石臼は家の軒下に据えられているのだが、この家ではなぜか家畜小屋の二階に置かれていたのだった。そしてその石臼から1メートルも離れていないところに、僕のベッドが置かれていた。
壁一枚を隔てているものの、目と鼻の先の距離で石臼をゴリゴリと回されていては、到底眠ることはできなかった。それでも僕はじっと我慢した。トウモロコシ挽きがそれほど急ぐ用事だとは思えなかったが、きっと彼女にも事情があるのだろう。それに10分もすれば、この作業も終わるに違いない。そう考えていたのである。
ところが10分経ち、20分経っても、石臼は止まらなかった。ついに我慢できなくなった僕は、隣で眠っているガイドのアルンを起こして(実は彼も起きていたのだが)、石臼を止めてもらうよう頼んだ。たぶん彼女は石臼を回すことが、僕らの迷惑になっていることに気が付いていないのだ。
案の定、アルンが扉を開けて女にひとこと告げると、石臼の回転はぴたりと止んだ。彼女は家畜小屋の二階に僕らが寝ていることを、うっかり忘れていたのだそうだ。「決して僕らに対する嫌がらせではありませんよ」とアルンは笑って言った。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| 朝一番の仕事は家畜に餌をやること。山羊がトウモロコシを食べていた。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
さすがに石臼を使って叩き起こされたのはこの一回だけだったが、人々が夜明け前から起き出して仕事を始めるのは、どの村でも同じだった。
もし睡眠障害に悩んでいる人がいれば、僕はネパールの農村を旅することをお勧めしたい。数日のうちに早寝早起きの規則正しい生活リズムが身に付くのは間違いないからだ。
まず最初に目を覚ますのは家畜たちである。鶏が景気付けの声を上げると、それを合図にして他の家畜も次々に目を覚ます。水牛がぶるぶるっと唇を振るわせ、山羊がカタカタと蹄をならし、犬が仲間に吠えかかる。
家畜の目覚めに合わせるようにして、人々も家の外に出てくる。ぼさぼさの頭をかきながら、トーストを片手に朝刊をめくる、なんてことはもちろんなくて、すぐに各自の仕事に取りかかる。母親は足踏み式の杵で米をつき、子供たちはほうきを使って家の内と外を掃いて回る。老人が家畜小屋から水牛を出し、父親が山羊に餌を与える。朝は農民にとってもっとも忙しい時間なのである。
こうして地平線の向こうから朝日が顔を出す頃には、もうすでに村にいる全員が目を覚ましているのである。仕事を持たない旅人である僕は、いつまで寝ていても文句を言われることはないのだが、このような雰囲気の中にいると、自然と目が覚めてしまうのだった。
|
|
|
 |
|
|
平和な農村の朝に、ちょっとした騒動が持ち上がったことがあった。夜明け前にトラが出て、山羊が一匹食べられてしまったというのである。
「トラなんて本当にいるのかい?」
僕は半信半疑でガイドのアルンに聞いた。ネパールでも野生のトラは激減していて、南部のジャングルにわずかに生息するだけだと聞いていたからだ。
「ええ、数は少ないですが、ときどき村を襲うことがあるんです。トラは人を襲いません。山羊や犬を食べるだけです。しかし村人にとっては大きな損害です」
アルンによれば、トラを殺すことは法律で禁じられているので、農民はトラが襲ってきても手を出すことができないという。せいぜい鍋や釜を叩いて、その音で撃退するぐらいしか方法がないのだが、実際にはあまり効果がないようだった。
トラの出現と同じぐらい恐ろしかったのは、毒蛇が出たときだった。こいつは僕らが縁側でお酒を飲んでいるときに突然現れた。庭で寝ていた犬が急に吠え始めたので、何ごとかと思っていると、家の主人が「毒蛇が出たんだ」と教えてくれたのである。
実際に毒蛇に噛まれると死ぬこともあるというから、人々にとってはトラ以上に恐ろしい存在なのだろう。男たちは棒を持ってヘビを追いつめ、叩き殺そうと躍起になっていたが、結局藪の中に逃げられてしまった。
|
|
|
「蛇といえば、思い出すことがひとつあるんですよ」
ベッドに横になったアルンが言った。
「あれは生まれて初めて映画を見たときのことです。僕が生まれた村には、3年前まで電気が通っていませんでした。だから映画やテレビを見ることができるのは、用事があって町に出かけたときだけだったんです。ポカラの町で初めて映画を見たのは、僕が10歳の頃だったかな。インド映画だったと思います。とにかく全てが驚きでした。映画というものが仮想世界の作り話だって知らなかったから、スクリーンの向こうにもこっちと同じように人がいるんだと思っていたんです。その映画に登場したのが、ものすごく大きな蛇だったんです。人を飲み込んでしまうような奴。それを見た瞬間、僕は恐ろしくて震え上がりました。あいつが僕に噛みついたらどうしようって、本気で心配したんです。でも隣に座っている友達は平然としているんです。彼はこの映画を見るのが二度目だったんで、ヘビはこっちへ出てこないって知っていたんです。だから僕も平気なフリを装わなくちゃいけなかった。でも本当は怖くて怖くて仕方なかったんです。あんなに怖い思いをしたのは、後にも先にもありませんよ」
その話を聞いて、僕はリュミエール兄弟が上映した世界初の映画を見た観客が、慌てて席を立って逃げ出したというエピソードを思い出した。それは蒸気機関車が画面の奥から手前に向かって走り抜けていく様子を撮影したもので、観客は列車が画面を突き抜けてこちらにやってくるに違いないと思ったのである。
その驚きから100年以上が経ち、僕らはスクリーンやテレビ画面を通じてバーチャルな世界と接することに何の違和感も感じなくなった。僕らの世代は生まれたときからバーチャル空間に取り囲まれて育ってきたと言ってもいい。
ネパールの山村もいずれそうなるのだろうか。たぶんなるだろう。灯油ランプが裸電球に替わり、テレビがやってきて、携帯電話やインターネットが使えるようになる。そんな時代がやってくるのは、そう遠くない未来なのかもしれない。
そうなったとき、ゴータレ村の長老が守りたいと言っていた独自の伝統文化は、きっと大きく姿を変えるに違いない。それはたぶん誰にも止めようがないことなのだと思う。
|
|
 |
|
 |