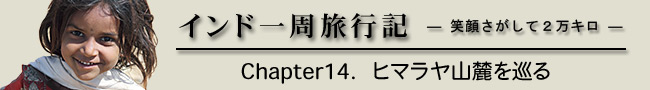|
 |
|
|
 |
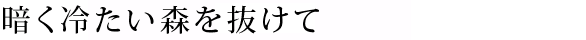 |
 |
 |
夜中まで降り続いた雨は、翌朝になってようやく上がった。
東の空からは生まれたてのように神々しい太陽が昇り、下界のものすべてをきらきらと輝かせている。鳥たちが勢いよくさえずり、農家からは朝食を作る煙がゆらゆらと立ち昇っている。
実に気持ちのよい朝だった。
「僕が約束した通り、晴れましたね」
朝のチャイを運んできたディアール君は得意顔だった。誰がどのような力を使ったにせよ、晴天は大歓迎だ。どうもありがとう。
僕はさっそく荷物をまとめてバイクに括りつけた。準備オッケー。さぁ出発だ。キーを回してエンジンをかける。
「必ずまた来てください。約束ですよ」
ディアール君はそう言うと、両手で僕の手を包み、深々とお辞儀した。最後までまったくインド人らしくない男だった。
カルソグの町で給油してから、再び山道を進む。景色は雄大だった。雪を抱いた山の頂と、見事な曲線を描きながら連なる段々畑。石造りの家屋がそこにアクセントを加える。自然と人の営みとが一枚の布を織るように絡み合い、ひとつ風景を作り出していた。
住民はヨーロッパ系の顔立ちをしていた。瞳が薄茶色で、鼻が高く、肌も白い。女性は花柄の服を着て、頭に手ぬぐいのような布をかぶっている。アジアというよりはむしろルーマニアやブルガリアなどの東欧の片田舎に近い雰囲気だった。
国道22号線に出て、再び急な峠道を登った。標高は2700mにまで達した。さすがにここまで高いところへ来ると寒さが身に染みた。ずっと暑い地域ばかりを旅していたから、防寒具らしい装備は何も持っていなかったのだ。Tシャツの上に長袖シャツを二枚重ね、その上にウィンドブレーカーを着込んでいたが、この寒さをしのぐには不十分だった。特に辛いのはハンドルを握る手だった。これほどの寒さだとわかっていたら手袋ぐらい買っておいたのに・・・。後悔先に立たず、であった。
ナルカンダという町を過ぎると、さらに道が険しくなった。断崖絶壁を削って作り上げた目もくらむような山道だ。車二台が苦労してすれ違えるほどの幅しかなく、誤ってコースを外れたりしたら数百メートル下まで真っ逆さまという恐ろしい道である。
|
|
|
こういう危険な道を走るときに必要なのは、こまめにクラクションを鳴らし続けることだ。交通量はとても少ないのだが(対向車とすれ違うのは数分に一度だけ)、見通しのきかないブラインドカーブでいきなりトラックとはち合わせる可能性もある。だから警笛を鳴らして注意を喚起しなければいけないのだが、問題は僕のバイクのクラクションの音がものすごく小さいことにある。トラックのクラクションが「どかんかい、ワレ!」とガラの悪いおっさんに怒鳴られているような迫力なのに対し、僕のバイクの警笛は良家のお嬢様が「あの・・・そこを通していただけますか・・・」と言うときのような遠慮がちな音なのだ。お行儀はいいのだが、実際の効果という点ではあまり期待できなかった。
断崖絶壁をしばらく進むと、深い針葉樹の森にさしかかった。そこには冬の間に降り積もった雪がまだ溶けずに残っていた。日光が地面まで届かないのだ。雪が溶けてぬかるみになった場所では、油断するとスリップしかねない。いつもより速度を落として慎重に進んだ。
尿意を催したので森の中にバイクを止めて、白い残雪の上にちょろちょと小便をかけていると、突然崖の上から「ゴゥゴゥゴゥ」という低いうなり声がした。
なんだ? 獣か?
とっさに頭を上げて崖の方を見たが、動くものの気配はなかった。
「ゴゥゴゥゴゥ!」
再びうなり声。さっきよりも大きくて太い声で、敵意が含まれているような気がした。こっちに近づいているのか?
僕はしばらく前に出会ったサドゥーが持つヒョウの毛皮のことを思い出した。彼は森でヒョウに襲われて、逆に斧で斬り倒したと言った。もしあの話がホラではなく本当だとしたら・・・そう考えると冷や汗が出た。
シカやイノシシじゃあるまいし、ヒョウなんて滅多にいるものじゃないとは思うのだが、近づきつつある声の主を想像するのは怖かった。僕は急いで小便を切り上げてバイクにまたがった。
以前、知り合いの女の子が「針葉樹林恐怖症」について話してくれたことがあった。彼女は松や杉などの深い森に入ると、恐怖に襲われて走り出さずにはいられなくなるという。空を覆い尽くす針葉樹の森には、確かに独特の怖さがある。底の見えない深い井戸を覗き込んでいるような得体の知れない不気味さ。人の力が及ばない闇の領域。そんなものを感じることがある。
それにしてもあの声の主はいったい何だったのだろう?
川沿いの町ロールに着いたのは4時半だった。日が傾いてさらに冷え込んでくる前に泊まる場所を確保できたので、ひとまずほっとした。
宿に荷物を置き、顔を洗ってから表に出てみると、5,6人の男が僕のバイクを取り囲んでいた。ヒマチャル・プラデシュ州では僕のバイクは常に注目の的である。この地域では販売されていない「謎のバイク」だからだ。
英語が話せる若者がいたので、彼がみんなを代表して僕に質問した。
Q「燃費は?」 A「リッター55キロだな」
Q「最高時速は?」 A「65キロぐらいかな」
Q「排気量は?」 A「70cc」
Q「ガソリンタンクの容量は?」 A「4リットル」
Q「値段は?」 A「27000ルピー」
思わず「俺はセールスマンかい!」と突っ込みを入れたくなってしまったが、僕の説明にいちいち大きく頷いている人々を前にすると、こちらもつい真面目に解説してしまうのだった。特に1リットルあたり55キロも走るという燃費性能には皆の衆もいたく感心した様子だ。しかしこれはあくまでも平地での数字で、ヒマチャル・プラデシュ州の過酷な山道だと50キロ以下に落ちるのだが。
一通り「謎のバイク」についての解説が終わると、若者が「試し乗りさせてくれない?」と言ってきた。いや、だからセールスマンじゃないんだってば!
しかし断る理由も特にないし、彼がバイクに乗ったままどこかへ消えてしまう心配もなさそうだったので、「どうぞ」とキーを渡した。
「すごく乗りやすいね。自転車みたいだ」
町をひと回りした若者の感想である。おっしゃるとおり。小さくて軽いがゆえの運転のしやすさは、このバイクの最大の長所なのだ。
「けど、やっぱりパワーが足りないな。俺のスクーターはね、燃費は悪いけど時速100キロまで出せるんだ。パワフルだろう?」
おいおい、曲がりくねった山道ばかり続くこの土地で時速100キロも出そうっていうのか? 正気か?
しかし若者が指摘したように、僕のバイクがパワー不足なのも事実だった。この70ccのギア無しバイクでヒマチャル・プラデシュ州の峠道を走るのは、無謀とは言えないまでも、バイクにかなりの負担を強いる行為であることは間違いなかった。
特に2000mを超える高地だとパワー不足は決定的なものになった。フルスロットルでも登りきれない急勾配では、バイクを押しながら歩く羽目にもなった。だからまぁヒマチャル・プラデシュ州でこのバイクを売っていないのは当然のことなのである。
ロールは1時間も歩けばひと回りできるほどのコンパクトな町だった。橋を渡った先にバスターミナルと市場があり、そこから斜面に沿って上へ上へと商店が連なっていた。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| 肉屋が並ぶ長屋。鶏、羊、豚など各種の肉が吊されている。長屋が大きく傾いている理由はよくわからない。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
町をうろうろと歩き回っているあいだに、同じ少女と三度もすれ違った。大きな布袋を担いで、ゴミを拾い集めている少女だった。貧しい家の子供なのだろう。学校にも通わず、毎日ゴミ拾いをして家計を助けているのだと思う。
僕と目が合うと、彼女は少し恥ずかしそうに微笑んだ。向こうは向こうで「ヘンな外国人がうろうろしているなぁ」と思っていたようだ。立ち止まってカメラを向けると、少女は戸惑いと恥ずかしさと嬉しさが入り交じったような複雑な表情でこちらを見つめた。
インドの子供はあまりはにかまない。屈託なく、感情をそのまま素直に表に出す。
しかしこの子は違った。小刻みに揺れ動く心のひだのようなものが、その瞳に映し出されていた。
|
|
|
|
|
|
|