|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
クアンバからイェンミンまでは九十九折りの山道だった。僕が乗っていたバイクは4段変速ギアなのだが、セカンドに入れないと進まないほどのきつい上り坂が続いた。それは一歩間違えれば谷底へ真っ逆さまという恐怖の道でもあった。ごく一部にはガードレールが敷設されていたが、その他の部分は「落ちたい人は遠慮なくどうぞ」という状態だったのだ。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| ベトナム最北部ハザン省の山道は、このような急カーブの連続だった。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
何の前触れもなく後輪がパンクしたのは、イェンミンの手前20キロのところだった。長旅をしていれば何度かパンクすることはあるし、すぐに修理屋が見つかれば何の問題もないのだが、今回はパンクした場所が悪かった。ほとんど人が住んでいない山奥だったのである。
結局、パンクしたままの状態でイェンミンまで走り続ける羽目になった。もちろんスピードは上げられない。20キロの距離を1時間半もかけてノロノロと進み、ようやくたどり着いたイェンミンの町外れの修理屋でタイヤのチューブを交換してもらった。パンクだけならパッチを貼るだけで直るのだが、空気なしで20キロも走り続けたためにチューブ自体がダメになってしまったのだ。それでも修理代金はたった3万ドン(230円)という安さだった。
そんなこんなで、イェンミンの町に辿り着いたときにはもう日が暮れ始めていた。今日はこれ以上進めそうもないので、この町で宿を探すことにした。
イェンミンは小さな町だったが宿は二軒あった。そのうちの一軒に入ってみると、部屋はあるという。値段も手頃だったのでここに決めようと思ったのだが、フロントの女の子が妙なことを言い始めた。
「パーミッションはありますか?」
と聞いてきたのだ。パーミッションってなに?
ベトナムの宿では、宿泊者はまずフロントにパスポートを預けることになっている。ベトナム人の場合はIDカードでOK。これは無賃宿泊を防止するための決まりらしい。しかしこの宿ではパスポートとは別にパーミッション(許可証)が必要だという。そんなものを要求されたのは初めてのことだったし、そもそも何の許可証なのかがわからなかった。
「あなたはパーミッションを持っていないんですか?」
彼女の表情が急に険しくなった。
「ノー。持っていません」
僕は肩をすくめた。
「それなら、泊めるわけにはいきません」
彼女はきっぱりと言った。「どうして?」と訊ねても、彼女は「パーミッションがなければダメ」の一点張りだった。
どうにも腑に落ちなかったが、これ以上粘っても無駄だろうと諦めて、もう一軒の宿に向かった。しかしそこでも対応は同じだった。許可証の有無を訊ねられ、持っていないことがわかると宿泊を断られた。その後はもっとひどかった。「許可証のない人間に構っている暇などない」とばかりに、フロントにいた男はさっさと奥に引っ込んでしまい、それ以降どれだけ大声で呼んでも誰も表に出てこなくなってしまったのだ。まるで疫病神のような扱いだった。
許可証を持っていない外国人はこの町に泊まることができない。どうやらそれがこの町を支配する鉄の掟のようだった。ハザン省はつい最近まで外国人の立ち入りを制限していた地域である。中国とベトナムは以前から緊張関係にあり、その国境地帯には外国人を入れたくないという政府の思惑が働いていたのだろう。許可証というのはその時代の産物だと思われる。
それにしても不思議なのは警察の対応だ。実はこのイェンミンの町に来る前に、僕は二度も警官に止められていたのだ。一度目は省都ハザンを出るときで、二度目はクアンバの町だった。どちらも僕を外国人だとは思わずに止めてしまったらしく、ベトナム語が通じないとわかると怪訝な顔をされたのだが、僕がポケットからパスポートを取り出して渡すと、ろく調べもしないうちに「もう行っていいよ」と軽く手を振っただけで通してくれたのだった。
もしこの地域に入るのに入域許可証が必要なら、検問の時にチェックするべきだろう。警察が入域を許可しているのに、宿屋が宿泊を断るというのはどう考えても理不尽な話だった。おそらく入域許可証の存在は、今では有名無実のものになっているのだろう。警察はもう許可証の有無を問題にしていない。あってもなくてもどちらでもいい。しかし宿の方は、万が一当局と揉めることになっては大変だと律儀に許可証制度を守り続けている。そんなところが真相ではないだろうか。
とにかくこの町には泊まれない。それだけははっきりしているのだから、他の町に移動するしかなかった。ただでさえ危険の多い山道を夜間に走るなんてことはできれば避けたかったのだが、そうも言っていられない状況に追い込まれてしまったのだ。
僕は地図を広げて、宿がありそうな町をチェックした。今まで走ってきた国道4Cをそのまま先に進めば、40キロ先にドンヴァンという町がある。もしくは来た道を50km戻ってクアンバで宿を探すことも可能だ。
考えられる選択肢はこのふたつだったが、僕はクアンバに戻る方を選んだ。この先のドンヴァンはベトナム最北の町であり、ここよりもさらに辺境なので、再び許可証が問題になる可能性が高かったからだ。
|
|
|
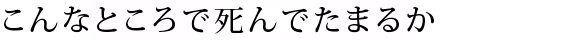 |
|
|
疲れはピークに達していた。
朝からずっと寒さに震えながらバイクを運転し続けていたし、ようやく休めると思った町で宿泊を拒否されてしまったから、もうヘトヘトだった。クアンバまで戻れば必ず宿に泊めてもらえるという保証もなかったし、いつまた雨が降り出すかという心配もあった。
そんな中、集中力を切らさずに夜道を運転し続けるのは至難の業だった。ベトナムの田舎道には街灯なんてものはなく、限られた範囲を照らすヘッドライトだけを頼りに走らなければいけないから、昼間の何倍もの注意力が必要なのだ。
こういうときは絶対に焦らないことだ。速度も抑え気味にして、慎重に走る。急がば回れの精神だ。僕は自分にそう言い聞かせながら走っていた。しかしそれは「少しでも早くクアンバに着きたい」という焦りの裏返しでもあった。
ヘッドライトの光の中に突然なにかが現れたのは、緩やかな左カーブを曲がっている途中だった。30センチほどもある大きな石だった。やはり集中力が散漫になっていたのだろう。石の存在に気付いたときには、すでにバイクは石まで数メートルの距離に接近していた。
やばい、落石だ!
僕は慌ててハンドルを右に切った。しかし避けた場所が悪かった。そこは舗装が剥がれて地面が露出し、しかも雨水でぬかるんでいた場所だったのだ。しまったと思ったが、もう遅かった。ブレーキをかけたものの、ぬかるみにはまったタイヤはすでにコントロールを失っていた。バイクは横滑りしながら、路肩の方へと流されていった。
一瞬の出来事だった。僕はバイクごと路肩の外に飛び出した。そして深い闇の中を落下していった。
よく大きな事故を起こした人が、「今までの人生がフラッシュバックした」と言うことがあるが、この時の僕もそれに近い状態だった。時間にすればコンマ何秒という短い間に、これまで目にしてきた様々な光景が一気に蘇ってきたのだ。まさに走馬燈状態。目の前は真っ暗なのに、僕に「見えている」のはとてもカラフルな映像だった。
俺はこのまま死んでしまうのか・・・。
そう思ったことを記憶している。この下が深い崖だったら当然無傷では済まないだろう。一応ヘルメットを被ってはいるが、そんなものは役に立たない。でも不思議と怖くはなかった。いずれにしても重力には逆らえないのだ。落ち始めたら、最後まで落ちるしかない。自分にはもうどうすることもできない。ここで死ぬのなら、それも仕方ないのかもしれない・・・。
ドスンという衝撃と共に、体が前方に投げ出された。受け身を取ったのか、取らなかったのか。僕は地面の上をゴロゴロと転がり、そして止まった。
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| 一歩間違えば数十メートル下へ真っ逆さま。そんな場所がいくらでもあった。 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
助かった。
そう思った。道路の下は崖ではなかったのだ。そこは田植えを控えた田んぼだった。柔らかい田んぼの土が衝撃を吸収するクッションになってくれたおかげで、僕はなんとか助かったのだった。
怪我もなかった。右腕と両足の膝にかすり傷がある程度で、それもたいしたことはなかった。骨も折れてはいない。あれだけのスピードで落ちていったというのに、痛みをほとんど感じなかったのが逆に不思議だった。
とにかく助かったのだ。ふーっと深くため息を吐くと、急にバイクのことが心配になってきた。僕はなんとか無事だったが、バイクが無傷というわけにはいかないだろう。もしかしたらここで旅を終えることになるかもしれない。でも周りは真っ暗なので、確認のしようがなかった。
そこにやってきたのが、近くの集落に住む人々だった。ただならぬ物音を聞きつけて、「何ごとだ?」と懐中電灯を持って集まってきたのだ。まるで演劇の舞台みたいに何本ものライトが一斉に僕を照らした。僕は「この通り大丈夫です」と言いながら、彼らに向かって手を振った。墜落したUFOから出てきた宇宙人はこんな気持ちになるんだろうか、とふと思った。
親切な村の若者4人が田んぼにめり込んだバイクを道路に引っ張り上げるのを手伝ってくれた。それから懐中電灯を借りてバイクの点検をした。驚いたことにあれだけの衝撃を受けたのにもかかわらず、バイクは致命的なダメージを免れていた。前輪のブレーキが壊れたり、ヘッドライトのカバーが割れたりはしていたが、エンジンにもフレームにも問題はなかった。キーを回してスターターを押すと、何ごともなかったようにドゥルルルとエンジンが動き始めた。信頼性の高いホンダを借りたのは正解だった。
「まぁ無事で良かったなぁ」
「あんた気ぃつけなさいよ」
言葉の意味はさっぱりわからなかったが、そんなことを言ってくれているのだろう。僕は親切な村人にお礼を言って、再びクアンバを目指して走り始めた。
本当の恐怖が襲ってきたのは、再出発からしばらく経ってからだった。冷静さを取り戻してから改めて振り返ってみると、自分がいかに幸運だったのかがわかってきたのだ。路肩の下が田んぼなどではなく、深い崖になっている場所はいたるところにあった。むしろ柔らかい田んぼになっている所の方がずっと少なかったのである。
僕は落下しているあいだに感じた「死んでも仕方ない」という諦めにも似た感情を思い出して、背筋の辺りに強い寒気を感じた。自分がそんな風に考えていたことが恐ろしかった。
「こんなところで死んでたまるか!」
僕は恐怖を振り払うように、声に出して叫んだ。
誰の耳にも届かない言葉が、闇の中に吸い込まれていった。
|
|
|
|
